持ち家として空き家を所有している場合、誰かに貸して家賃収入を得ようと考える人も多いのではないでしょうか。持ち家を貸すという賃貸ビジネスは、個人でも比較的簡単に始められます。
個人でも家を貸すことで利益をあげた場合は「所得」となり、課税の対象です。不動産賃貸業を行った時は具体的にどのような税金がかかるのでしょうか。また確定申告は必要なのでしょうか。家を貸した時の税金について知っておきましょう。
戸建賃貸経営については以下の記事をご覧ください。
家を貸す場合にかかる税金について

自分の持ち家を貸したとしても、それはアパート経営やワンルームマンション投資などと同じ、立派な不動産賃貸業です。不動産賃貸業を行って収益をあげた場合、必ず税金が発生します。
不動産にかかってくる基本的な税金とはどのようなものがあるのか、その種類と特徴について、しっかり理解を深めましょう。
まず、家を貸すことについて詳しく知りたい方は以下の記事も一緒にご覧ください。
不動産所得に対しての所得税
不動産で収入が上がった場合は、所得も上がりますので所得税として課税される金額もそれに比例して上がります。また、家賃収入などで利益がでた場合は確定申告が必要です。
所得税とは
所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの所得に対して個人にかかってくる税金のことです。「所得」と聞くと、「1年の間で稼いだお金すべて」のことだと考えてしまう人も多いですが、実は所得と収入は異なるものです。
所得はあくまでも収入の中から必要経費と呼ばれるお金を差し引いたもののことです。例えば、賃貸営業を行った際の不動産所得の場合、「収入」として含まれるのは家賃、駐車場料金、更新手数料、共益費、礼金などです。
そこから、固定資産税、管理費、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利息などが「必要経費」として差し引きされます。残ったものが「所得」として課税の対象になります。
確定申告が必要
確定申告とは、個人の総所得を税務署に報告することを言います。会社員として働いている場合、会社側が源泉徴収という形で税務署側に所得を報告しています。しかし、個人でサイドビジネスなどを始めて利益が出た場合は、そこで得た所得については自ら税務署へ申告を行う必要があります。確定申告期間にすべての総所得を申告し、その年の税額が決定するという仕組みになっています。
不動産ビジネスに関しては、所得が年20万円を超えた場合は確定申告を行う必要があります。確定申告を忘れてしまったり、確定申告期間を過ぎてしまったりすると、ペナルティーとして無申告加算税と呼ばれる追徴課税が発生します。
所得によって変わる住民税
所得税の他にも、所得が上がったことによって課税の金額が変わってくる税金として「住民税」があげられます。住民税の課税率は一定ですが、毎年かかる税金のため、きちんと把握しておきましょう。
住民税とは
住民税とは、県や市などの地方自治体に収める税金のことです。基本的には、前年度の総所得をベースとして課税額が決まり、税率は一律、課税所得の10%と決まっています。こちらも所得税と同じく、会社員であれば毎月、自動的に給料から天引きされ収められていることが多いです。
住民税は所得税と違い、不動産業で得た収入に対して直接かかってくる税金ではないのですが、金額や内容を把握しておくことが大切です。
また、サイドビジネスなどを始めて1年の総所得が上がった人は、前年度と比べて金額が上がる可能性があるため、あらかじめ納税資金を確保しておきましょう。
確定申告する必要はない
住民税に関しては、所得税とは違い、個別に確定申告をする必要はありません。これは所得税の確定申告をした時点で、自動的に地方自治体に対して総所得と課税額を申告したことになるためです。
住民税の納付の方法は2通りあり、給与から源泉徴収される特別徴収と、自分で直接納付する普通徴収があります。普通徴収の場合は、一括で納付する方法の他に、年4回に分けて納付するというやり方もできます。
不動産などの固定資産に対する固定資産税
不動産を所有していると必ずかかってくる税金として固定資産税があげられます。課税金額が不動産の価値によって変化するので、土地のオーナーは税額や支払い方法を必ず把握しておき、払い忘れのないように気をつけましょう。
固定資産税とは
固定資産税とは、その年の1月1日時点で所有している不動産(固定資産)の所有者に対してかかる税金です。不動産の中には、土地だけではなく、住居や店舗なども含まれているので、不動産賃貸を行う場合も毎年かかる税金です。
固定資産税の税率は一律ではなく、不動産の価値によって課税額が変わってきます。つまり、不動産の価値が高ければ高いほど、納める税金の金額も高くなります。
固定資産税の納税方法
固定資産税は市区町村から毎年4月から6月頃に送付される納税通知書に従って納付します。納付方法は2通りあり、一括で支払うか、年4回の分割で支払う方法があります。
国民年金では、一括払いや前納をすると税額が割引をされますが、固定資産税は一括払いであっても割引のシステムはありません。一括払いのメリットが特にないため、年4回の分割払いで支払う方法が一般的です。
支払い方法は、各市区町村で少しの違いはあるものの、現金、クレジットカード、口座振替、Pay-easy(ペイジー)、電子マネー(nanaco、WAON)の5種類があります。
固定資産税と合わせて課税される都市計画税
都市計画税は固定資産税と合わせて課税されることが多いため、聞きなれない方も多いかもしれません。しかし、市街化区域内に不動産を所有している場合は必ず課税されますので、把握しておきましょう。
都市計画税とは
都市計画税は、その年の1月1日時点で市街化区域内に不動産を所有している場合に課税される税金のことです。固定資産税と同時に課税されることが多いため、混同して考えられがちですが、全く別のものです。
固定資産税はその不動産が市街化区域内にあるかどうかは関係なく課税されるのに対し、都市計画税は基本的に「市街化区域内にある土地や建物のみ」を課税対象としています。
また、固定資産税は新築住宅に対して減税の制度を設けており、都市計画税の場合はその土地を「住宅」として使用する場合に減税される場合があります。
細かい点は市区町村によって違うため、各地方自治体に問い合わせをするとよいでしょう。
都市計画税の納税方法
都市計画税は固定資産税とまとめて課税されるため、大まかな納税方法は固定資産税と同じです。毎年4月から6月頃に地方自治体から送付される納税通知書に従って納付し、また納付方法も一括で支払うか、年4回の分割で支払うかを選ぶことができます。
分割払いを選んだ場合、納付期限が市区町村によって異なります。
「今持っている不動産を現金化したい」という方は、売却という形で手放すという選択肢もあります。一括査定サイト「イエウール」を使えば、無料で最大6社から査定を受けられるので高く売ってくれそうな会社が分かります。
不動産所得の確定申告について
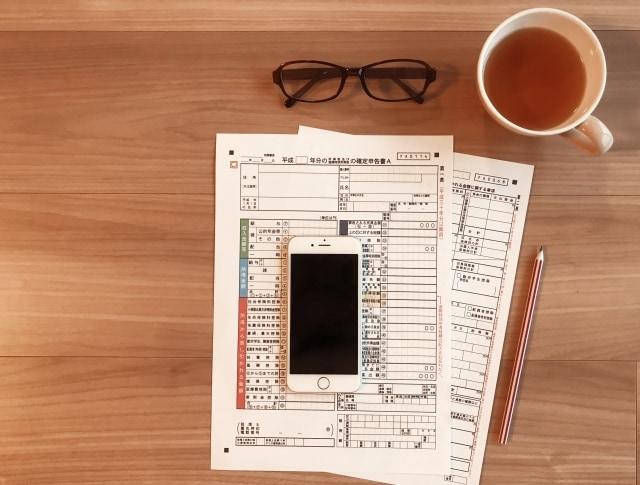
不動産で所得を得た場合は、確定申告は義務です。申告をしないとペナルティが発生するため、きちんと理解しておきましょう。
確定申告の流れ
会社員の人であれば、自分で確定申告をしたことがないという方も多いかもしれません。ここでは、申告の流れを説明します。
記載前に準備するもの
まず一つ目のステップとして、全ての必要書類をそろえることが大切です。確定申告にまず必要なのは、「確定申告書B」「不動産修士内訳書」「所得税青色申告決裁書」の3点です。こちらは、国税局のホームページか管轄の税務署からダウンロードできます。
さらに、現在も会社員として働いている人の場合は、勤務先からの源泉徴収も提出する必要があります。不動産投資という形での不動産ビジネスをしている場合は、賃貸契約書や通帳など、家賃収入や必要経費があることを証明する書類も用意しておきましょう。
書類集めは意外と時間がかかり、量が多くて見落としてしまいがちなので、不備のないよう事前にしっかり準備しましょう。
決算書などの書類作成する
書類を集めたら、次は書類の作成に取り掛かりましょう。確定申告の際に大切な書類は「決算書」と「申告書」です。決算書は、1年間の不動産収入から必要経費を引いた不動産所得を記載したものです。こちらに書かれている金額をもとに、申告書に所得税額を記載します。
「確定申告書B」には青色申告と白色申告という2種類の書類があり、一般的には、白色申告の方は決算の手続きがシンプルですが特別控除が受けられず、またビジネスが赤字になってしまった場合は繰り越しができません。
青色申告の場合、最大で65万円の特別控除が受けられます。また、家族への給料を経費として計上することもでき、赤字になってしまった場合でも3年間は繰り越しできるというメリットがあります。これらのことから、青色申告で確定申告を行うことをおすすめします。税務署に申請する
作成した書類は税務署へ申請しましょう。自分がどこの税務署に提出しなくてはいけないのかは、国税局のホームページで調べることができます。
提出方法には3通りあり、税務署に直接持参、郵送、またはe-Taxというオンラインサービスの利用が可能です。
申告期限を守る
確定申告をする際、心がけておきたいことは必ず申告期限以内に提出することです。確定申告は、納税者が自分から税務署へ自分の所得及び税額を申告し、納付するというシステムです。
そのため、申告をしなければいけない人が申告を怠ったり、申告期限を過ぎてから申告すると法律違反となります。
うっかり忘れてしまったり提出期限が過ぎてしまったりすると、「加算税」や「延滞税」といったペナルティが発生するため、申告は必ず期限以内に行いましょう。
賃貸経営で節税対策しよう

賃貸経営をすることで減税されるケースがあります。所有している土地を有効活用することで節税ができるので、家を貸したいと考えている人は、効果的な節税対策についても知っておきましょう。
アパート経営で節税対策
所有している土地を活用し、賃貸アパートなどを建設して賃貸業を経営した場合、その土地を更地のままで所有している時よりも減税されることがあります。
例えば、土地を所有していれば毎年必ずかかる固定資産税と都市計画税ですが、アパートや住宅などを立てることによって減税されるため、何も建っていない状態の時と比べて最大で1/6までの減税が可能です。
また、土地を相続する際にかかってくる相続税も、賃貸用のアパートなどが建っている土地を相続する場合は更地の土地を相続するよりも安くなります。
相続税は、対象の土地の価値によって課税率が変わるという特徴があります。建物は年月がたつと劣化するため、他人に貸すことで所有者が自由に使えないという権利の制約が生まれ、更地の時よりも賃貸物件が建っている土地は地価が低く評価されます。そのため相続税が安くなるのです。
土地活用は業者に相談
空き家を含め、土地の活用を考え始めた時、税金対策や節税対策など、考えることや知らなくてはいけないことがたくさんあります。
初めて土地活用をする場合や、周りに詳しい人がいない場合は、専門家に相談をするというのも一つの手段です。土地活用は長期的な事業となるため、1社だけに相談せず、必ず複数の業者から見積もりやプランの提案をしてもらうようにしましょう。
節税対策をした上でしっかり納税しよう

家を貸すという土地活用方法は、うまく運営することができれば大きな収益をコンスタントに運んできてくれる大切な資金リソースになります。
しかし、賃貸経営を始めるにあたっては大きな金額が動くことが多く、またそれに伴って毎年かかってくる税金も高くなります。不動産の賃貸業を始めたときに、「こんなはずではなかった!」とならないよう、税金についてしっかり理解することが大切です。
土地活用での節税対策を考えた場合、イエウール土地活用をオススメします。こちらは、日本でも有数の賃貸経営比較サイトです。一括資料請求サービスの提供とともに、賃貸経営に関する不安やお悩みを解決できるような情報も充実しています。
記事のおさらい
他にも戸建賃貸経営についてのノウハウを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

