「ガレージハウス経営って具体的にどんな賃貸経営?」、「ガレージハウス経営のメリットとデメリットには何があるの?」、「ガレージハウスの建設にかかる費用はどれくらい?」
ガレージハウス経営について、他の賃貸経営に比べ聞きなれないことから、上記のような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。本記事では、そのような疑問を解消できるように、ガレージハウス経営について基礎から詳しく解説しています。
- 居住部分とガレージが一体となっている家を貸し出して賃料収入を得る土地活用
- 稀少価値が高く需要が供給を上回っている
- 「高収入が得られる」「安定収入が得られる」「節税効果を得られる」といったメリットがある
- 一方で、「高い費用がかかる可能性がある」「需要はあるがターゲットが広いわけではない」といったデメリットもある
- 設計のコツは「自分が住みたい、自分の愛車を保管したい」と思えるものにすること
- 建築基準法、税金、法的問題に注意が必要
ガレージハウス経営とは

ガレージハウス経営とは、居住部分とガレージが一体となっている家を貸しだして、賃料収入を得る土地活用方法です。
ガレージ付きの賃貸物件は一般的ではないため、一定の層を中心に高い需要を見込めると人気を集めています。
主なガレージハウスの形態としては、1階にガレージ、2階に住宅といった形態が主流です。都心の場合は土地が狭い場合が多く、多くのガレージハウスはこのような階層構造で建築されます。広さに余裕がある土地では、ガレージを別で建築することもありま
す。
その他、土地活用のアイデアについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
ガレージハウスに需要はあるのか
ガレージハウス経営を検討している人が最も気になるのが、「ガレージハウスに需要はあるのか」といったところだと思います。結論から言うと、需要は大いにあります。
ガレージハウスは、大切な車やバイクを安全に保管しながら生活できることが一番の特徴ですが、近年では様々な使い方をされています。例えば、サーフィンやキャンプなどの大きな道具の保管場所として、クリエイターのアトリエとして、富裕層のセカンドハウスとして、などが挙げられます。
このように、ガレージハウスは人々のライフスタイルによって適した使い方ができるため、幅広い層のニーズに応えることができるのです。
市場規模は大きくなっている
近年日本では、働き方改革やワークライフバランスの推進、新型コロナウイルス感染症拡大などが原因で、就業時間や制度が見直されたり、リモートワークなどの新しい働き方が定着したりしました。
その影響で、密を避けて移動できる車やバイクの有用性が高まり、それらを保管できる場所を必要とする人が増えています。また、ガレージハウスは車の愛好家だけではなく、ジオラマ作成やDIYなどの趣味を楽しみたいといった人からも注目を浴びていて、セカンドハウスとしても需要が高まっています。
このように、ガレージハウスの使い方は人それぞれで、ニーズの多様化が進んでいます。認知度も徐々に上がっているため、今後さらに市場規模が大きくなっていくことが予想されます。
需要が供給を上回っている
ガレージハウスはその名の通り、ガレージのついた住宅という付加価値のついた建物であるため、アパートやマンションとった一般的な賃貸経営と差別化を図ることができます。
そして、先述した通りガレージハウス経営は徐々に需要が高まっていますが、それに対して供給できる物件が少ないというのが現実です。新しい物件が出てから部屋が埋まってしまうまでが早く、空きを待ち望む入居希望者が一定数いるような状況です。
このようにガレージハウスは希少価値が高いため、多少賃料が高くてもすぐに入居者を確保することができます。完全に流行っているわけではないこのタイミングが、ガレージハウス経営を始める良いタイミングと言えるでしょう。
ガレージハウス経営のメリット

ガレージハウス経営のメリットは、主に以下の4つです。
- 高収益を見込める
- 安定した収益を保ちやすい
- 節税ができる
- 立地条件に左右されにくい
高収益を見込める
ガレージハウス経営は以下の2つの理由から、高収益が見込めます。
- 家賃の設定を高めにできる
- 建築費用を抑えることができる
家賃の設定を高めにできる
ガレージハウスは主に、高級車やバイクなどを趣味とする高所得者層からのニーズが多いです。
そのため、こうした一部のユーザー向けとなるガレージハウス賃貸物件の流通規模は、一般的な戸建賃貸物件などと比較すると少なくなります。
このように、供給より需要が多い点に加えて、高所得者層に入居希望者が多い点から家賃を周辺相場よりも高く設定することができます。
建築費用を抑えることができる
一般的な住宅建築においては、耐震性などの安全面や居住空間を考えた結果、建築費用が高くなってしまうことが多いです。
もちろん、高級車やバイクなど趣味に関連した使われ方が多いガレージハウスでも、頑強な家作りは重要です。
しかし、趣味性が高くセカンドハウスとしての活用も多いガレージハウスでは、一般的な住宅のような居住設備や空間を必要としない場合が多いです。
そのため、建築面積を少なくすることができ、結果として耐震性や防犯性を考慮に入れても、一棟当たりの費用を抑えることができます。
安定した収益を保ちやすい
ガレージハウス経営が安定した収益を保ちやすい理由は、長く住みたいと考える人が多いためです。
ガレージハウスは物件数が少ないため、ガレージハウスに住んでいる人がすぐに他のガレージハウスに引っ越すことは少ないです。そのため、たとえ空室となったとしても、引く手あまたな状況のガレージハウスが空き家になる可能性は低いといえます。
このように、賃貸経営における大きなリスクである空室リスクを回避しながら、経営を行うことができます。
節税ができる
ガレージハウス経営においても、一般的な住宅経営と同様に以下のような税金を減らすことができます。
- 土地の固定資産税・都市計画税
- 相続税
土地に居住用の建物を建てると、住宅用地の特例が適用され課税標準額が更地の1/6となります。また、計算に使う課税標準額が固定資産税と同じである都市計画税にも住宅用地の特例が適用されることによって更地の
1/3ほど節税することができます。
相続税では、ガレージハウスを建てることによって土地にかかる評価額を約20%にまで押し下げることができます。
土地活用による節税について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
立地条件に左右されにくい
2拠点生活をしている人、日常生活で公共交通機関を使う機会のない人、退職後は趣味をゆっくり楽しみたい人など、ガレージハウスに住みたいと考えている人は多くいます。
これは、ガレージハウスが趣味性の高い住宅であるということが大きく関わっています。ガレージハウスに住みたいと思う人は、車やバイクを趣味にしていることが多いことはご承知の通りです。一般的な賃貸経営の場合は、日常生活に欠かせない便利なスーパーなどの施設や交通の便が重視されます。そのため、立地の分が悪いと買い手がつかなかったりして、長期的に安定した収益をあげることが難しくなります。
その点、ガレージハウスに住む人は車などで移動することが多いため、駅やスーパーから遠いことがさほどデメリットにはならないことが多いです。そのため、一般的な賃貸物件ほど、立地条件を気にする必要はなさそうです。
ガレージハウス経営のデメリット
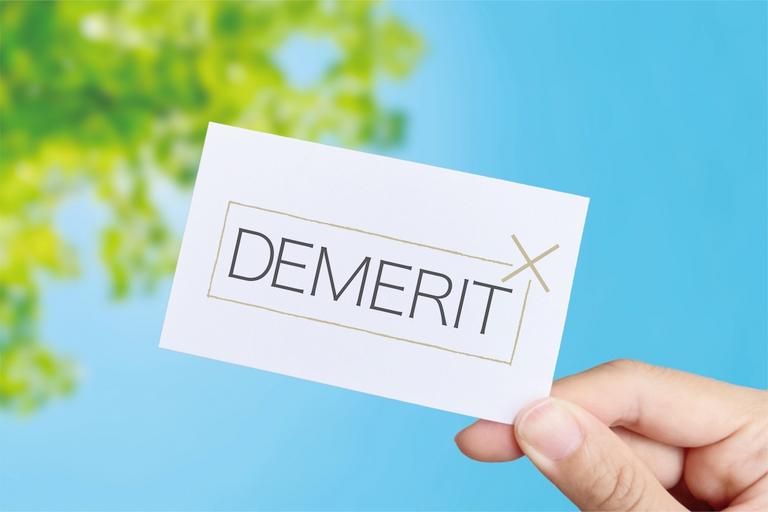
ガレージハウス経営のデメリットは以下の3つです。
- 運用実績が少ない
- 住宅環境にこだわると費用がかさみやすい
- ガレージハウス経営を行っている会社が少ない
- ターゲットを細かく設定する必要がある
順番に解説していきます。
運用実績が少ない
ガレージハウス経営という土地活用のニッチな分野においては、一般的な戸建て経営などに比べてデータが少ないというデメリットがあります。
ガレージハウス経営においては何が正解なのか、何がダメなのかといった情報が不足しているため、経営していくにあたっては常に手探りをしながら進めていくことになります。いくら高収益に期待できて、安定した需要が見込めるといっても、このように運用実績が少ないガレージハウス経営では、思った通りにいかない可能性があります。
一般的な土地活用にあるような、成功に近づくためのテクニックのようなものが存在しません。そのため、ガレージハウス経営をするときには、信頼できる不動産や建築会社と相談をしながら進めていく必要があります。
ガレージハウス経営を行っている会社が少ない
現状、ガレージハウスに精通している不動産会社やハウスメーカーは多くありません。
一般的なハウスメーカーでもガレージハウスを建てることはできます。しかし、運用実績が少ないため、建築様式から募集までイメージ通りに進めてくれる業者は少ないです。
地元にある不動産会社やハウスメーカーに加えて、不動産情報サイトなどを使い幅広く業者をみることがポイントです。
住宅環境にこだわると費用がかさみやすい
ガレージハウスは、ガレージの広い空間の実現のために頑丈な素材を使わなければならないため、建築費が高くなってしまうことがあります。
また、ガレージの住宅環境にこだわると、費用がかさむ可能性が高いです。例えば、ガレージハウスに住みたいと考えている人は、車やバイクを安全に保管したいと思っているはずです。そうすると、防犯対策はしっかりとなされている必要があります。
加えて、ガレージ内のライフラインに関する設備など、利用したいと考える人のニーズによってかかる費用が変化します。このように、ガレージハウス経営に関するデータが乏しい分、逆に費用がかさみやすいといったことも考えられます。
ターゲットをより細かく設定する必要がある
趣味性の高い住宅形態であるガレージハウスは、ターゲット設定をどのようにするかによって物件スタイルや設備が大きく変わり、さらには経営開始後の空室リスクを回避しやすくなります。
例えば、セカンドハウスとしての利用を考えていて、車が趣味であれば車1,2台分ほどの広さのあるガレージやそのセキュリティ性、居住環境についてもある程度予想される設備に最低限の投資でコストを抑えることが可能です。
空室リスクと建築コストを抑えるためにも、ターゲット設定は細かく行っておきましょう。
所有する土地でどのような土地活用種別が良いのか迷ったときは複数の土地活用プランを一括請求・比較できるサービスを使うことをお勧めします。
イエウール土地活用なら、複数のプランを比較して収益性の高い土地活用方法を見つけることができます。
\最適な土地活用プランって?/
ガレージハウスの設計のポイント

ガレージハウスへの入居を考えている人は、「愛車をどれだけ安全で清潔な状態で保管できるか」、といったところにこだわっています。そのため、どのような設計にするかがとても重要となります。
自身が車を所有している人であれば、自分が愛車を保管したいと思えるような設計にするのが良いでしょう。本章ではガレージハウスの設計におけるポイントを、参考までにいくつか紹介しています。
- 車庫スペースを充分に取る
- 外壁材は経年劣化に強い材料を使用する
- 窓やドアには断熱性・防犯性の高いものを使用する
- シャッターをリモコン操作できる仕様にする
- 排気ガスや換気対策を考慮する
- 空調を設置する
- 防音対策をとる
- 壁や床は汚れが付きにくい材料を使用する
- 室内から車を見れる仕組みにする
- 居室部分の日当たりや風通しを考慮する
車庫スペースを充分に取る
ガレージハウスは車庫をメインスペースとするため、車を余裕をもって出し入れできるスペースの確保が大切です。
天井を高くすることで有効な収納スペースを確保したり、奥行きに余裕を持たせて自転車やバイクなども置けるようにしたりといった工夫も重要です。
また、車庫の出入り口の幅も広めに確保すると良いでしょう。具体的にいうと、大型車が入るような設計にすることによって、競争率の高い物件にすることが可能です。
外壁材は経年劣化に強い材料を使用する
ガレージハウスの外壁材には、経年劣化に強い材料を使用しましょう。耐久性が高く、かつメンテナンスが比較的容易な素材がガレージハウスの外壁材として適しています。また、塗装によって防水性を高めることもおすすめです。
ガレージハウスの立地や周辺環境によっては、外壁材に要求される条件が異なることがあります。例えば、海岸の近くや湿地帯などの湿気や塩分の多い環境では、そういったものに耐性のある素材を選ぶ必要があります。
窓やドアには断熱性・防犯性の高いものを使用する
窓やドアを断熱性の高いものにすれば、外部の冷気や熱が室内に伝わりにくくなり、気密性が高まるため冷暖房効果も上がり、省エネ・光熱費の削減にも役立ちます。
また、防犯性の高い窓やドアにすることで、ガレージハウス内の愛車や住人の安全を守ることができます。防犯ガラスや強化ガラス、セキュリティロック、ドアホンやインターホンなどが挙げられます。
シャッターをリモコン操作できる仕様にする
シャッターをリモコンで操作できる仕様にすることは、利便性の観点でとても重要なポイントになります。
リモコンで操作することで車内からシャッターを開けることができますし、わざわざ手動で開閉するという手間をとる必要もありません。特に、雨の日や寒い時期には手動での開閉は避けたいところでしょう。
排気ガスや換気対策を考慮する
ガレージハウスについて、排気ガスや換気対策はとても重要です。車の排気ガスは有害物質を含んでいて、密閉された空間で車両を保管している場合、換気不足で室内の空気が悪くなる可能性があります。
最悪の場合、車庫内の換気が不十分だと居室にまで臭いが入ってしまいます。そうならないために、ガレージの奥に換気扇を配置することをおすすめします。
また、排気ガスを効率的に排出する、排気ファンや排気ダクト、排気口などをうまく配置することも考えると良いでしょう。
空調を設置する
ガレージ内に空調を設置することもポイントの一つです。
ガレージ内に空調を設置することにより、暑い夏や寒い冬に車内の温度が過度に上下することを防ぐことができます。また、車庫内で作業をする際は、快適な室内空間を確保することもできます。
ガレージはただの車庫ではなく、人が長時間滞在する可能性のある場所ですので、ふさわしい場所にするために空調は必要なのです。
防音対策をとる
防音対策を取ることが、近隣住民とのトラブルを避けることにおいて重要になります。
入居者が深夜や早朝に車を出し入れする場合は、シャッターの開閉音などのせいでクレームを貰うことがあります。
そのため、ガレージの床に防振材を使用して騒音を軽減したり、できる限り開閉音が静かなタイプのシャッターを選択することが重要です。
壁や床は汚れが付きにくい材料を使用する
ガレージハウスの壁や床を汚れが付きにくく、清潔に保ちやすい材料を使用することで、入居者から需要の高い物件になります。
また、床を防水性をのある素材にしたり、排水設備を設けることで、洗車の際に水の浸透を防ぐことができます。車庫内で洗車ができることはかなり重要なポイントの一つですので、しっかりと検討しましょう。
室内から車を見れる仕組みにする
車庫を室内から車を見れるギャラリー仕様にすることで、車が好きな人にとっては車を眺めることのできる満足度の高い空間になります。
具体的には、車庫スペースの内側に壁を設置する場合は、一部をガラスなどの透明な材料にすることで室内から見ることができます。
車庫内を人感センサー付き照明にして、近くを通った時に車がライトアップするようにしておくことで、よりギャラリー感が増して良いかもしれません。
居室部分の日当たりや風通しを考慮する
ガレージハウスにおいては車庫スペースがメインとはいえ、居住スペースの快適性も忘れてはいけません。
日当たりを確保するために居住部分を南向きに配置したり、クローゼットや収納スペースなどの配置を考えて空気の循環を促したりしましょう。
また、快適な睡眠の確保をするため、寝室と車庫の位置を離すことも重要です。
ガレージハウス経営の注意点

ガレージハウス経営において、注意すべき点について紹介します。
- 建築基準法
- 土地の用途制限
- 税金や法的問題
- 建築の依頼先
建築基準法
ガレージハウスの建築の際は、建築基準法などの法律や規制を守る必要があります。
例えば、ガレージの内装は防火素材を使用する義務があり、木材を使用する場合は天井・壁の面積の10分の1以内と定められています。また、地域によって防火性能を有する外装にする義務があります。
これらを守らない場合、建築物の安全性が脅かされると同時に、法的な問題に発展する可能性があるため注意しましょう。
土地の用途制限
用途地域によって、容積率や建ぺい率が定められています。用途地域とは、都市計画法に基づき、土地を住居系や商業系・工業系などの用途に応じてエリア分けしたものです。
容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合のことで、建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合のことです。住居系の場合、容積率は50%~500%、建ぺい率は30%~80%となっていますが、前面道路の幅の影響を受けたり地域によって異なったりするため、予
め確認しておくと良いでしょう。
市街化区域においては用途地域が必ず定められていて、そのエリア内で建築することのできる建物の種類や大きさが決まっているため注意が必要です。
税金問題
ガレージハウス経営では、ガレージ部分も建物の延床面積に含まれます。しかし、建築基準法では、ガレージ(車庫)部分は建物の延焼面積の1/5まで容積率にカウントしないという決まりがあり、これによって固定資産税も減るのではという解釈につながっているようです。
固定資産税は建物の売買価格の7割に1.4%をかけたものによって決められます。つまり、この建築基準法とは何も関係がありません。ガレージを建築したところで建物にかかる固定資産税は通常の戸建て賃貸に比べ節税することはできませんので注意してください。
ただし、土地にかかる固定資産税は住宅用地の特例によって節税できます。よって、正しくは建物の固定資産税は節税できないが土地の固定資産税は節税できる、となります。
建築の依頼先
ガレージハウスの建築の際、どこに依頼するのかといったことも考えておかなければなりません。依頼先に関しては主に以下の3つがあります。
- ハウスメーカー
- 設計士
- ガレージハウス専門の工務店
ハウスメーカーは様々なスタイルの住宅を建設しているため、ガレージハウスの建築も依頼することができます。対応エリアの広さや建物の品質保持などが特徴です。
自分の中で既に明確な間取りプランが決まっているなら、設計士に依頼して設計してもらうのも良いでしょう。その設計図を元に建築会社に建ててもらうことで、自分の希望するガレージハウスが出来上がります。
おすすめは、ガレージハウス専門の工務店に依頼することです。専門としているため、多くのアイデアを持っていて、車やバイクが好きな人の希望をよく汲み取ってくれます。
ガレージハウスの建設にかかる費用
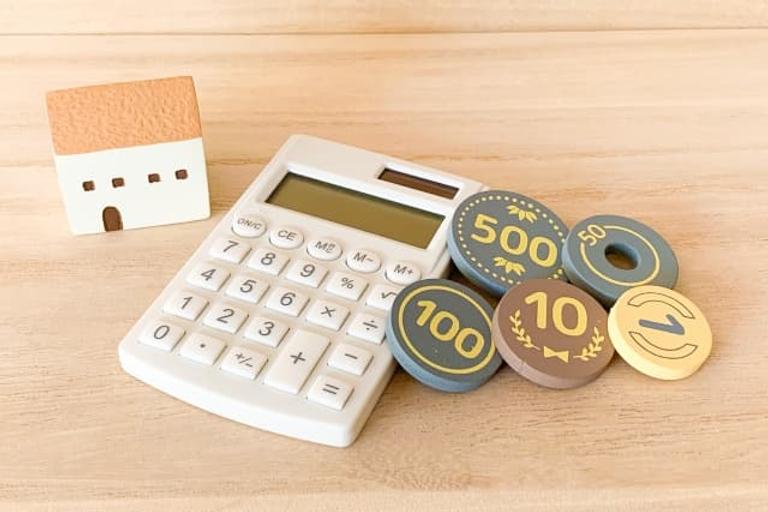
ガレージハウス経営を始めるつもりであれば、ガレージハウスの建設にかかる費用を把握しておく必要があります。
ガレージハウスの建設には以下の費用がかかります。
- 調査費
- 建設設計費
- 建築工事費
調査費
ガレージハウスの建設にかかる費用について、まずは調査費について解説します。
調査費は測量費と地盤調査費に分けられ、具体的な要件や計画によって異なります。また、前提として地域や専門家の料金によって費用が異なることは覚えておいてください。
測量費
測量費とは、土地の面積や地盤レベル、道路の幅員などを明確にするための調査にかかる費用です。測量は現況測量と確定測量の2種類があり、現況測量が10万円~20万円、確定測量が35万円~90万円が相場となっています。
現況測量とは、ブロック塀などの境界を基準にして見た通りの土地の面積などを測り、おおよその土地の寸法・面積・高さを調べることができます。建物を新築する場合はこの現況測量を行なうことになり、費用は土地の面積によって変わります。
一方確定測量とは隣地の所有者に立ち会ってもらい、正確な土地の面積を測るものです。これは主に土地を売買する際に行なったほうが良い測量となります。
地盤調査費
地盤調査費とは、建物を建てる前に地盤の状態を確認するための調査にかかる費用です。
地盤調査は地盤の強度や安定性、地震や台風への耐性などを確認するために行われ、建物を建てる際は実施する必要があります。調査の結果地盤に問題があると判断された場合、必要に応じて地盤改良工事を行ないます。
地盤調査費には専門家の調査料や地盤調査機器の使用料などが含まれ、相場は10万円~50万円ほどと言われています。
建設設計費
ガレージハウス経営の建設設計費は、建築設計に関する費用のことを言います。調査費と同じく、地域や設計事務所の料金体系によって費用が異なります。
建設設計に費の内訳について説明します。
設計管理費
設計管理費とは、ガレージハウスを建てる際にかかる設計費と工事監理費のことです。設計管理費は、本体工事の1割程度が相場となっています。
設計費とは、敷地の状況や法的規制を考慮したうえでプランを立て、必要な場合は役所へ届け出を出したり、間取りや設備を決めて予算に応じた見積もりを出したりなどの、さまざまな作業にかかる費用です。
工事監理費とは工事をつつがなく進めるためにかかる費用のことで、工事の実施からスケジュールの管理、完成後の引き渡しの立ち合いまで、様々な工程があります。
建築確認申請諸費用
ガレージハウスを建てる際は、役所に設計図書などを添付して建築確認申請を提出する必要があり、それらにかかる費用が建築確認申請諸費用です。
まず、建築の計画が建築基準法やその他の条例に沿っているかの審査をしてもらい、工事完了時の完了検査に合格すると建物として認めてもらえます。
建築確認申請はその手続きのこと言い、15万円~50万円ほどの費用がかかります。
建築工事費
建築工事費とは、実際にガレージハウスの建築にかかる費用のことです。建築工事費に関しても、地域や建築の規模、使用する建材や設備の品質によって費用が変わります。
内訳について解説していきます。
本体工事費
本体工事費とは、建物そのものを建築するためにかかる費用です。基礎工事や骨組み、壁、内装、その他設備、人件費などもこれに含まれます。
本体工事費は坪単価で計算されることが多く、ガレージハウスの場合は80万円~100万円が坪単価の相場です。
外構付帯工事費
外構付帯工事とは、建物本体以外にかかる費用のことを意味していて、ライフラインを引き込むための整備費や、駐車場・堀などが必要になった場合の外構工事費が該当します。
外構工事費はその土地の面積やインフラの整備環境などによって大きく変わります。電力や水道が通っていない場合、電気を引いたり上下水道管の給排水工事をしたりから始めなければならないため、工事費は高額になるでしょう。
地盤改良工事費
地盤調査の結果、地盤に問題があると判断された場合地盤改良工事が行われます。地盤が弱い場合、地盤沈下や建物の倒壊を防ぐために地盤の強化は必須になります。
地盤改良工事な内容は地盤の強度によって変わります。問題のある地盤が地表から近い場合は地表面からセメント系の固化材を使用して固めますが、深い場合は杭、柱状改良等各種工法を検討したうえで地盤を補強します。
地盤改良工事費に関しては、敷地の面積や工事の内容によって異なり、地表から近くの改良なら少なくて30万円、地表から深い改良なら多くて180万円ほどすることがあります。
ガレージのみにかかる費用の相場
ガレージの建築のみにかかる費用については、坪単価で48万円~80万円が相場です。
以下は普通乗用車で想定した、収容台数ごとに必要な坪数と費用相場です。
- 1台:4坪~5坪 190万円~408万円
- 2台:8坪~10坪 475万円~800万円
- 3台:15~20坪 725万円~1,200万円
ガレージハウス経営は今狙い目の賃貸経営!

ガレージハウス経営は、賃貸経営のなかでも根強い需要があることから空室リスクも少なく安定した収益に期待できると注目されています。
しかし、持っている土地の性質や周辺環境、信頼できそうな業者などガレージハウス経営をする上で重要な要素はいくつかあります。今回ご紹介したポイントを確認しつつ、自分に最適な土地活用法をみつけていきましょう。

