アパート経営を考えている人にとって「いつになったら初期費用を回収できるのか」「何年後に黒字になるのか」は多くの人が気になるところです。どのくらいで黒字になるのかが分かればアパートを建設する際にどのくらいの費用をかけたらいいのか目安になってくるでしょう。本記事ではアパート経営をする際にどのくらいの期間で黒字になるのか細かくシュミレーションしていきます。
アパート経営の利回りについては以下の記事をご覧ください。
アパート経営が黒字化するのにかかる年数
アパート経営が黒字になるまでにかかる年数は、目安として10年です。アパート建築費、購入価格、家賃設定、空室率など経営状況によって変わってきますが、巨額の初期費用が発生するので最初の数年は赤字覚悟が必要です。早く資金回収をしようと焦るのではなく、長期的な視点でアパート経営の収支計画を考えてみましょう。
アパート経営が黒字になるまでのシュミレーション
アパート経営をおこなう上でキャッシュフローという言葉を覚えておきましょう。
キャッシュフローとは家賃収入から経費やローンの返済額、税金を差しいたときに実際に手元に残るお金のことです。このキャッシュフローが初期の投資金を上回れば黒字化したと考えます。
では実際に「何年後」黒字になるのか、以下の物件を情報を目安に黒字になるまでの流れをシュミレーションしてみましょう。
| 戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 物件価格 | 5,200万円 |
| 初期費用(頭金を除く) | 300万円 |
| 年間家賃収入 | 600万円 |
| 表面利回り | 10% |
| 購入時の自己資金 | 1,500万円 |
| 融資金額 | 4,000万円 |
| 融資金利 | 2.0% |
| 融資期間 | 20年 |
| 諸経費率 | 20% |
| 空室率 | 12% |
| 年間キャッシュフロー | 166万円 |
年間家賃収入528万円{600万円×88%}-362万円{支出の計算経費120万円{600万円×20%}+ローン返済額242万円}=166万円
アパート経営初年度(赤字)
ここでは累計のキャッシュフロー1500万円(自己資金額)を上回ることが黒字化の条件とします。アパート経営1~2年目はアパート建築費や購入費以外に、保険などの諸経費にお金がかかるため、ほとんどの場合が赤字になります。アパート経営をする上で具体的にどのような経費が掛かってくるのかは以下の章でまとめています。
アパート経営4年目(回収率44%)
アパート経営4年目終了時点のキャッシュフローは664万円{166万{年間キャッシュフロー}×4}になります。初期投資額から664万円を差し引くと836万円です。アパート経営4年目にして半分近くの投資金を回収できていることになります。
アパート経営8年目(回収率89%)
アパート経営8年目終了時点のキャッシュフローは1328万円{166万{年間キャッシュフロー}×8}になります。初期投資額から1328万円を差し引くと172万円です。アパート経営8年目、投資金の回収は目の前です。
しかし、10年を目前にしたこの辺りで各種設備の不備、壁や床の変色など経年劣化が目立ち始めます。基本的にこういったケースの修繕費の負担はオーナーもちになります。投資金の回収目前で予想外の出費に悩まされることもあるでしょう。
アパート経営10年目(黒字)
アパート経営10年目終了時点のキャッシュフローは1660万円{166万{年間キャッシュフロー}×10}になります。初期投資額1500万円を160万円上回ったので黒字化したといえます。
アパート経営が黒字化する流れはこのようになります。黒字化するには最低でも10年はかかります。とはいえ、今回のシュミレーションはあくまでも計算上のもの。実際にはアパートの空室率増加であったり、家賃の減額で思った以上に家賃収入が得られなかったり、経年劣化などで思わぬ出費が重なることもあります。アパート経営を始める際は、そのようなリスクなども頭に入れておきましょう。
アパート経営に必要な経費まとめ
アパート経営を黒字化させるのに、10年前後かかることがわかりました。次に気になるのが10年もの歳月をかけて回収しなければならないアパート経営開始時に発生する初期費用の内訳です。ここでは、アパート経営を始める際に発生する費用の種類やそれぞれの費用目安を見ていきましょう。何にいくらかかるのかが分かれば、黒字化までの収支シュミレーションがおこないやすくなります。
アパート購入(建築費)
アパート経営の基盤となる物件の購入や建築にかかる費用です。初期費用の大部分を占めます。アパートの購入額は物件の状態や立地で異なりますが3000万円~購入することができます。
建築時にかかる費用は購入時よりも高くなります。本体工事にかかる費用は、構造・ハウスメーカーによって異なりますが目安として「木造で坪77~97万円、鉄骨造で坪84~104万円程度」です。さらに本体工事とは別に別途工事費用(地盤改良、給排水、空調・電気・ガス、外構工事など)が本体工事のおよそ20%ほどかかります。
その他の費用
アパート経営を始める際には、物件の購入費や建築費以外の費用も発生します。購入費や建築費は銀行からの融資を受けて、ローンを組むことができますが、諸用費は借りられないため自分で用意する必要があります。諸用費は建築費のおよそ5%が目安になります。
以下の表が諸用費の内訳になります。建築時の費用によって変わってくるので目安として確認してください。
| 測量費用 | 30万前後 |
|---|---|
| ローン手数料 | 5~10万円 |
| 火災保険・地震保険料 | 建築費の0.5% |
| 印紙代 | 1~3万円 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額(建築費の5~6割程度)×0.4% 債権金額(借入金額)×0.4% |
| 司法書士報酬 | 6~7万円 |
| 不動産所得税 | 固定資産税評価額×3% |
なお、固定資産税評価額とは固定資産税の基準となる評価額のことで建築費の5~6割程度であることが多いです。
アパート経営を始める可能性が出てきたら、複数の企業にプランを提案してもらうのがおすすめです。
なぜなら、アパート経営は建築費の見積もりや賃料設定など経営プランによって収益が1,000万円以上変わることもあるからです。
建築費がいくらなら収益性の高いアパート経営ができるのか、利回りはどのくらいが適切なのか、気になるところを建築会社に相談してみましょう。
日本最大級の土地活用プラン比較サイトイエウール土地活用なら土地所在地を入力するだけで複数の大手ハウスメーカーのアパート経営プランを一括請求することができます。
\最適な土地活用プランって?/
活用事例:長期安定経営を考えた 病院の職員寮



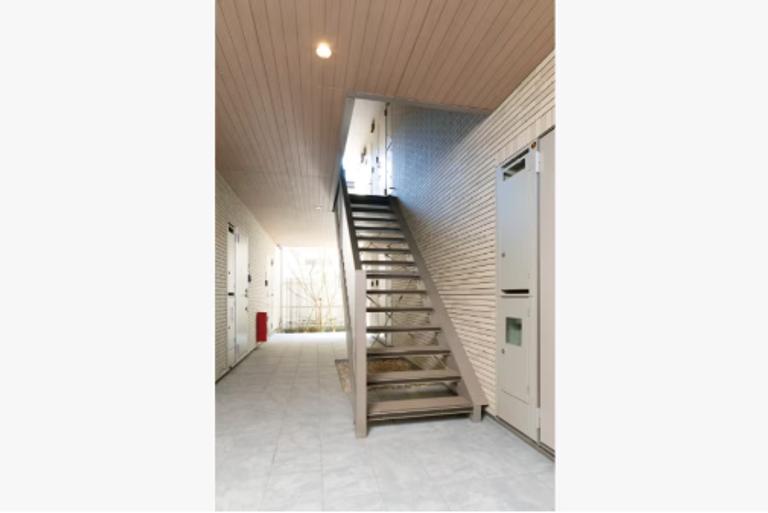

| 土地面積(㎡) | 403.91 |
| 延べ床面積(㎡) | 455.34 |
今回訪問したのは、飲食店経営などを手がけているオーナーさまによる医療従事者のための職員寮です。徒歩5分の場所にある病院から、昨年増床し職員も増えたため職員寮を建ててほしい、との要望がありました。
「30年前からこの病院の職員寮として別の土地で賃貸住宅を所有しています。1棟目が上手くいったことで2棟目を建て、2棟とも病院が借り上げ、管理の手間なく長期的に安定経営できていることから、駐車場だった土地を活用して3棟目を建てることにしました」。
病院とは30年に渡る長い信頼関係があり、医療という業種柄、地域で長く必要とされることから、この先も病院の職員寮を建てることで安定経営ができると考えました。
近年病院に限らず、人材確保の面から福利厚生を充実させるため、魅力的な社員寮を確保したいと考える企業が増えています。
病院からは、他の賃貸住宅よりも魅力的で長く住みたいと感じてもらえるように、さまざまなリクエストがありました。(ミサワホーム株式会社の土地活用事例)
アパート経営を黒字化する3つのコツ
アパート経営はシュミレーションでは10年で黒字化するというものになりますが、実際に黒字化させるにはちょっとしたコツが必要です。ここではアパートを黒字化させるためのポイントを解説していきます。
地域のターゲットを見極める
アパート建築時(購入時)に、その土地の市場調査を行い、借主になるであろうターゲットを見極めることが大切です。このターゲットを読み違えれば、どれだけ立地がよく新築であっても借主が見つからず空室が目立ってしまいキャッシュフローは減ってしまいます。
例えば、大学が立ち並ぶ学生街で4LDKのファミリー向けの物件を経営してもなかなか借主は見つかりません。これらは完全にターゲットを読み違えてしまった結果です。このような失敗に陥らないためには、地域の特徴からターゲット層が学生であることを見極め、1DKのシンプルな部屋の間取りで価格帯の安い家賃を設定しましょう。空室率を下げることで少しでもキャッシュフローを良くするのがアパート経営を黒字化させるコツになります。
ランニングコストを削らない
アパート経営をする上でかかってくる、税金や修繕費、リフォーム費、共用部の電気代などの費用がランニングコストです。少しでも支出を抑えたい気持ちはわかりますが、アパート経営においてランニングコストを削りすぎるのは黒字化を遠ざける原因の一つです。
ランニングコストには削減することのできない税金の他、ローンの返済や管理会社に払う管理委託費用の他、削減が可能なアパートの修繕費、リフォーム費用、共用部分の電気代や設備維持費用などがあります。少しでも早く黒字化させるために削減可能な費用を削ってしまうと、目先の節約はできても長い目でみるとかえってキャッシュフローは悪化し、赤字になってしまいます。例えば、古くなった蛇口やシャワーへッドを取り換えなければそれだけで水周りの印象は清潔感のないものになり入居者が減ってしまうでしょう。古くなった設備を新しいものに取り換える、こうしたランニングコストを削らず物件のイメージを良く保つことで空室率を下げることができ、結果として黒字化につながります。
キャピタルゲインのタイミング
キャピタルゲインとは、資産の価格が上がることによって得られる収益のことです。アパートもオーナーの資産です。アパートの近くに駅ができたり、イオンモールのような大きな大型スーパーができえばその地域の利便性が向上し、アパートの価格も上がることがあります。物件の価値が高くなるタイミングで売却をすれば建築時、購入時と比較してアパートを高く売ることができます。これがキャピタルゲインです。いつアパートを売っても黒字になるわけではないので周辺環境の変化に応じたタイミングが大事です。アパート経営は永久に続けられるものではありません。経年劣化で維持が難しくいつかアパートを手放さなければならなくなるときがきます。出口戦略を考えていく中でアパートを売却するタイミングを見逃さないこともアパート経営を黒字化させるコツの1つといえるでしょう。
アパート経営のリスクと対策
アパート経営にはリスクがつきものです。上記のシュミレーションのようにとんとん拍子にことが進めばいいですが、そうはいかないのが現実です。ここではアパート経営におけるリスクと対策を解説します。
空室になるリスク
空室になるリスクとは、入居者が決まらない部屋(空室)が発生し、一時的にその部屋分の収入が途絶えるリスクです。空室度合を示す指数を空室率といい、空室率が高い状態が続くと赤字になってしまいます。
部屋が埋まらないのには何か原因があるはずです。周りの物件や同じアパートの他の部屋と比較して原因を探してみてください。根本的な原因を解決することができればいいですが、日当たりや周辺環境などどうにもならないことはその部屋だけ家賃を下げるなどの対策を施してみましょう。
老朽化するリスク
アパートの老朽化が原因でアパートの壁や柱、土台などの躯体の修繕が必要になり費用負担が増えるリスクです。アパートを建ててから10年くらいを目安に劣化が目立ち始めます。
とにかく、こまめな修繕修復と点検が大事です。壁の小さなひび割れも、放置しておくことでどんどんと割れ目は広がっていきます。早い段階で設備の不備を見つけることができれば少額の出費で済むものも、対応が遅れると高額な修繕費になることもあります。
修繕のリスク
アパートの躯体部分ではなく、水周りやエアコンなどの設備の修理、修繕が増えることによるリスクです。基本的にアパートに備え付けになっている設備の修理費用は入居者(住人)ではなくオーナー持ちです。
ガス給湯器やエアコン、水回りの設備類は5~10年の間に修理や交換が必要になります。一定期間を過ぎたタイミングで一気に修正や交換の依頼が発生することでオーナーの頭を悩ませます。しかし、こうした設備も細かな手入れで少しでも長く使ってもらうことができたり、定期的な点検で修理、交換を行っていれば一度に大きな出費を負担をしなくて済みます。
災害に遭うリスク
災害に遭うリスクとは地震、家事、台風など災害全般を含めたリスクのことです。日本は地震大国、建築年数が経過した物件は地震発生時、倒壊。いつどこで災害が起こるかわからないので新築アパートでも中古アパートでもアパート経営をする上では避けられないリスクになります。
地震のリスクはアパートを設計するうえで耐震性の高い構造にすることで多少のリスクは抑えられます。その他の自然災害に備えるには地域のハザードマップを確認しましょう。アパートを建てる段階で土砂崩れの起きる危険地域は避ける、洪水などが発生しやすい場所はエントランスは高めに設置する、1階部分の住居を避けるなどアパート設計時に相談してみましょう。
金利が上昇するリスク
金利が上昇するリスクとはアパートを建設、購入する際に融資してもらった銀行からのローンの金利が上昇し、ローン返済額が増え返済が難しくなるリスクです。
このリスクを伴うのは変動金利で借りている場合のみです。最初から固定金利設定を選択することで、金利上昇リスクを回避することができます。
滞納されるリスク
入居者が家賃を払わずに滞納し、本来得るはずだった収入がゼロになるリスクです。アパートの戸数が多く規模が大きいと、家賃をなかなか払わない入居者もでてきてしまうことがあります。
家賃滞納を防ぐために、ほとんどのオーナーは入居者に家賃保証会社への加入を義務付けています。もしくは、入居者に敷金として家賃2か月以上を先に支払ってもらう、万が一の際に家賃を請求できるよう連帯保証人をつけさせることでリスクを最小限に抑える工夫をすることができます。
賃料が下落するリスク
築年数が一定数経過したり、空室が多いと家賃を見直さなければ入居者の募集が厳しくなることがあります。
一度下がった家賃を上げるのは難しいです。築年数が経過するにつれて家賃が下落するのは避けられないかもしれませんが、そのリスクを見越して、収支計画を立てること、時には練り直しをすることも必要です。また、築年数が経過した物件であっても、リノベーションやリフォームを行うことで、一見きれいなまま維持することはできます。維持費や修繕費を削らずに定期的な設備投資を行うことで長期的に安定したアパート経営をすることができるでしょう。
アパート経営を始めようか考えたとき、どのようにアパートを設計すればいいのか見当がつかないのではないでしょうか。
例えば2階建てにするか3階建てにするか、間取りの設計をどうするかについては土地の条件やアパート経営の目的によって変わります。
日本最大級の土地活用プラン比較サイトイエウール土地活用なら土地所在地を入力するだけで複数の大手ハウスメーカーからアパート経営プランの提案を受けることができます。
\最適な土地活用プランって?/
まとめ
アパート経営を始めるなら最初の情報収集が重要です。日本最大級の土地活用プラン比較サイトイエウール土地活用なら、土地所在地を入力するだけでアパート経営のプランを取り寄せることができます。

