「駐車場は建物の建築費がない分、利回りが高くなるのでは」と駐車場経営について検討している人もいるかもしれませんが、駐車場経営は固定資産税が収益を圧迫することがあります。駐車場経営を検討しているのであれば、固定資産税を含めた収支計画を考える必要があります。
それでは、駐車場経営における固定資産税がどのくらいかかり、どう試算すればよいのでしょうか。本章では「駐車場の固定資産税はいくら?」という疑問に答えつつ、住宅用地との違いや節税策までを徹底解説します。
また、よく聞く「駐車場の固定資産税は住宅用地の6倍になる」といった情報の真偽についても解説しています。
駐車場の固定資産税の計算方法
駐車場の固定資産税は、課税標準額(固定資産税評価額)に標準税率の1.4%をかけることで求められます。固定資産税評価額は一般的に地価公示価格の70%となっています。これらを式で表すと以下のようになります。※固定資産税評価額=地価公示価格×70%
固定資産税評価額は、毎年市区町村から送付される納税通知書によって確認が可能です。
ところで、駐車場の固定資産税が住宅用地の6倍になるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、実は厳密にいうとそれは誤りです。
それでは本章では、固定資産税の仕組みから住宅用地の特例、負担調整措置の説明も交えて、なぜ「駐車場の固定資産税は6倍になる」という誤りが広まっているのか、そして実際6倍にはならない仕組みまで解説していきます。
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有する土地・家屋や償却資産などの固定資産に対して課せられる地方税の一つです。納付の時期は地域によって異なりますが、一般的には4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けるか一括で納付します。
毎年市区町村から送付される納税通知書の送付時期に関しても自治体によって異なりますが、一般的には4月~6月に送付されます。納付書は固定資産税課税台帳に登録されている人宛てに届く点に注意しましょう。
納付先は固定資産のある市区町村となりますが、東京23区内関しては東京都が納税先です。市区町村では市町村税、東京都では都税として固定資産税を納めます。
駐車場と住宅用地の違い
駐車場は更地と同じ評価になるため、住宅用地と違い軽減措置の特例が適用されず固定資産税が高くなります。住宅用地とは住宅やアパートなどの、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地のことです。そして、その住宅用地の固定資産税と都市計画税の税率を緩和する軽減措置のことを住宅用地の特例と言います。
地方税法の第394条3の2において、詳しい要件を確認できます。東京都のホームページによると、住宅用地の定義が以下のように定められています。
- 1.居住用としての土地で、その上に建つ建物の総床面積10倍までの土地
- 2.併用住宅(一部を賃貸にしている建物など)の土地であれば、一定割合を乗じて算出される面積の土地
上記の定義に対する具体例として、専用住宅やアパートの敷地、住宅用建物の敷地と一体となっている庭や自家用駐車場が挙げられます。ここで言う駐車場とは、居住用の家屋が立っている土地内の駐車場のことです。賃貸駐車場をはじめとして、店舗や事務所、工場などの敷地、資材置場などは住宅用地としては認められません。
駐車場ではなく人の住むための土地である「住宅用地」の場合は、固定資産税を軽減する特例が認められています。住宅用地かどうかは、土地の所有者が自由に決められるものではなく、地方税法によって「居住用の建物のため敷地である」と認められる必要があります。
住宅用地の特例による軽減措置
次に、住宅用地の特例によって実際にどのくらい固定資産税が軽減されるのかを解説します。また、なぜ駐車場の固定資産税が住宅用地の6倍と言われるのかについても説明します。住宅用地には「小規模住宅用地」「一般住宅用地」といった二つの種類があり、それぞれに適用条件があります。適用条件と、どのくらい軽減されるかは以下の通りです。
| 小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分) | |
|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額×1/6 |
| 都市計画税 | 課税標準額×1/3 |
| 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) | |
|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額×1/3 |
| 都市計画税 | 課税標準額×2/3 |
上記の表から、土地が「小規模住宅用地」に当てはまる場合は課税標準価格が1/6になるため、固定資産税がかなり安く抑えられます。そしてこれが、「住宅用地の特例を受けられない駐車場の固定資産税が、住宅用地よりも最大6倍高くなる」と言われる理由です。
負担調整措置が取られるため「6倍」にはならない
土地の固定資産税は時価の高騰と共に高くなるため、土地の評価額が急に上昇したときそのまま税額も上がらないようにするための措置があります。それが負担調整措置です。そしてこの負担調整措置こそが、駐車場の固定資産税が住宅用地の6倍にならない理由です。
負担調整措置では負担水準を計算することで課税標準額が決まります。以下が負担水準の求め方です。
負担水準額が70%超える場合は、当該年度の評価額の70%を課税標準として算出します。そして、一般的に負担水準は70%を超えることが多いため、課税標準額は評価額に70%をかけた値であることがほとんどです。
そのため、土地が住宅用地の特例で課税標準額が6分の1になったとしても、負担調整措置によって駐車場の固定資産税も軽減されているため、単純に6倍にはならないのです。
駐車場経営を始める前には、一度収入や費用を確認しておくようにしましょう。駐車場経営は節税対策にならない分、実際に始まってから固定資産税の支出によって赤字経営になってしまうなんてこともあります。
そのため、あらかじめ駐車場経営のプロに相談しておくことが大切です。契約するまでは無料で相談でき、実際の収益イメージを確認して「やっぱりやめる」といったことも可能なので、安心して利用してみてください。
\建築費は?初期費用は?/
活用事例:円阿弥4丁目第2大栄駐車場

駐車場の固定資産税シミュレーション
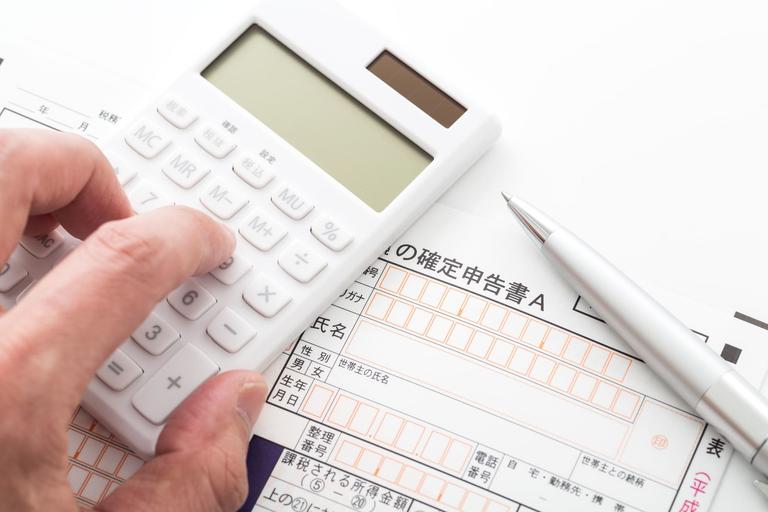
本章では、駐車場が賃貸住宅と一体となり住宅用地の特例が適用される場合にかかる固定資産税と、駐車場のみの場合にかかる固定資産税についてのシミュレーションを行なっています。
住宅用地の特例が適用された場合
以下の条件で土地を所有しているケースの固定資産税をシミュレーションします。- 東京都板橋区板橋1丁目に200㎡の土地(課税標準額5,800万円)
- 総床面積100㎡
- 新築住宅(課税標準額800万円)
新築住宅は固定資産税額を1/2にするという特例がありますので、それを踏まえると、以下の計算式になります。
| 建物の固定資産税 | |
|---|---|
| 固定資産税 | 5,800万円×1.4%=11万2,000円 |
| 軽減後の固定資産税軽減 | 11万2,000円×1/2=5万6,000円 |
| 土地の固定資産税 | |
|---|---|
| (5,800万円×1/6)×1.4%=約13万5,000円 | |
建物の固定資産税+土地の固定資産税=固定資産税の総額
試算の結果、建物と土地の固定資産税を合計すると19万1,000円が住宅用地としての課税額となります。
住宅用地の特例が適用されない駐車場の場合
次に、住宅用地の特例が適用されない場合に固定資産税がどのくらいか試算してみます。| 駐車場の固定資産税 | |
|---|---|
| 固定資産税 | (5,800万円×70%)×1.4%=56万8,400円 |
住宅用地が適用されない駐車場の固定資産税は、56万8,400円が課税額になります。
建物がある土地と駐車場の固定資産税の比較
上記の試算をもとに、住宅用地と駐車場でどのくらいの違いが出たか確認してみましょう。今回のシミュレーションで分かった通り、駐車場の固定資産税が住宅用地よりも高くなるのは事実ですが、6倍になるというのは誤った情報です。一般的には3倍~4倍になります。
実際の納税額を知りたい!固定資産税の調べ方

住宅用地と駐車場の固定資産税にどれだけ違いがあるかを解説してきました。
固定資産税を算出するためには、課税標準価格や実際の計算方法を確認する必要があります。詳しい固定資産税の納税額の確認方法は主に4つです。
「固定資産税の納税通知書」で確認する
最も簡単な方法は、毎年4~5月に送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」で確認することです。納税通知書には土地や建物ごとの価格に加えて、計算方法まで記載されています。書類を保管している方は目を通してみましょう。
納税通知書を破棄していたら「固定資産税証明書」を発行する
もし固定資産税の納税通知書を紛失、破棄してしまった場合、所有する土地を管轄する市区町村の役場で「固定資産税評価証明書」を発行することで確認できます。その際に注意すべきは以下の3つです。
- 手数料が数百円かかる
- 土地が2筆以上に分かれている場合はその分の手数料がかかる
- 納税義務者や所有者等しか発行できない
「固定資産課税台帳」を確認する
固定資産税証明書を発行するほかに、「固定資産課税台帳」を確認する方法もあります。この方法でも、納税義務者や所有者などの関係者しか閲覧できない上、手数料がかかります。
駐車場経営を検討している場合、「固定資産税路線価」から試算する
駐車場経営のために、土地の購入を検討している人は、「固定資産税路線価」から試算する方法があります。「一般財団法人 資産評価システム研究センター」が提供している「全国地価マップ」で固定資産税路線価を簡単に調べることが可能です。例えば、土地の面する道路に「269000」と記載されていた場合、「1㎡あたり26万9,000円」です。100㎡の土地であれば2,690万円が土地の評価額になります。最後に上記で算出された評価額税率をかけて計算するだけで、おおよその固定資産税額を確認できることになります。
固定資産税を払えるくらいには土地の活用をしたいと考えている方は、土地活用のプロにまずは相談してみましょう。土地の価格や毎年かかってくる固定資産税額を元に、収益プランを試算して提案してくれる企業もそろっています。まずは、簡単な入力を済ませて土地活用の企業から無料で資料を取り寄せてみましょう。
固定資産税は駐車場の設備にも課税されることがある
駐車場経営を行なう場合、土地のみではなく設備にも課税される可能性があります。
アスファルトや精算機、屋根や車止めなどが設備の例ですが、これら設備の取得費用が150万円を超えると、固定資産税の一種である償却資産税が課税されることになります。
償却資産税は土地や家屋以外の機材や設備にかかる税金のことで、毎年申告を行なって償却資産台帳に登録する必要があります。償却資産税の算出方法については以下の通りです。
因みによくある疑問として、「砂利敷きの駐車場とアスファルトの駐車場の固定資産税は違うのか」というものがありますが、土地の固定資産税自体はどちらでも変わりません。
ただし上記で説明した通り、アスファルトのような設備には償却資産税がかかる可能性がありますので、その違いは理解しておくようにしましょう。
駐車場でも固定資産税は節税できる!

固定資産税が一般の住宅地より6倍も高いとなれば、駐車場経営のモチベーションも下がってしまうかもしれません。
しかし、駐車場でも住宅用地として認められて節税できる場合もあります。
駐車場とアパートなどの土地を繋げる
住宅用地の定義について簡単に解説しましたが、駐車場の定義に節税のヒントが隠されています。冒頭に紹介した東京都が定めている住宅用地の定義を引用して、紐解いてみましょう。- 住宅用地及びその特例措置について(住宅用地とは)
- 住宅用地の例:住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場
住宅用家屋が「専用住宅」と「アパート等」で分けられており、住宅用地の例の最後に「住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場」とあります。つまり、土地を建物と駐車場で一体利用していると認められる駐車場であれば軽減措置が受けられるのです。
償却資産税の発生を防ぐ
駐車場設備の取得にかかった費用が150万円を超える場合、償却資産税が発生することは2章で説明しました。逆に設備の取得を150万円以内で済ませれば、償却資産税が発生することはなく節税になるはずです。
広い土地でのコインパーキング経営は、設備の取得に150万円を超える可能があります。こういった場合に償却資産税の発生を防ぐためには、土地の半分をコインパーキングにし、もう半分を月極駐車場にするという方法があります。
このようにすることで、駐車場の設備の取得にかかる費用を下げることができ、150万円を超える可能性を下げることができます。
駐車設備を一括償却資産にする
「取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として3年に渡り均等償却ができる」という制度があります。
そのため駐車場の設備にこれを適用させれば、総額150万円以上かかった設備についても償却資産税を発生させずに済むことができます。
例えば、18万円の車止めを10個購入したら総額180万となり償却資産税が発生します。これを3年間に渡り60万円ずつ計上していくことで償却資産税の課税がされず、節税することができるのです。
まとめ

「駐車場=固定資産税が高い」と考えられていますが、固定資産税の仕組みや軽減措置、特例を知ることで節税が可能です。こうした特例を適用するためには、市区町村への申告が必要な場合が多くあります。地域によって申告の期限が異なることもあるため、適用を検討するなら市役所などで確認しましょう。
税法はルールが細かく定められています。手続き方法や詳細な納税額を知りたい方や複雑な権利関係がある方は土地活用のプロが集う一括診断「イエウール土地活用」を利用して、信頼できる不動産会社や企業へ相談する方法がおすすめです。イエウール土地活用の一括診断を活用して、土地活用を成功させましょう!

