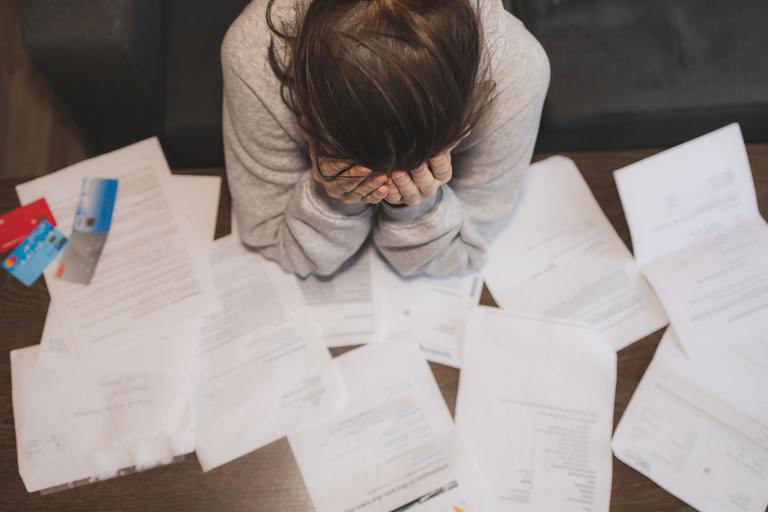仕事をしながらでも取り組みやすいマンション経営に興味を持つ人が増えています。
その一方で、投資初心者などが詐欺のターゲットにされるケースがたびたび発生しています。中でもワンルームマンション経営は初心者に始めやすいというイメージが強く、詐欺や詐欺まがいのことが横行しています。怪しい不動産業者を見抜き、詐欺の被害にあわないためにはどうすればよいのでしょうか。
当記事では、マンション経営で多い詐欺のパターンや実際に合った詐欺の事例、注意したい営業担当者の言動などについて紹介します。また、「詐欺にあったかもしれない」と思った際の対処方法も併せて解説します。
ワンルームマンション経営の詐欺でよくある手口5つ
不動産投資に関する詐欺は、昔から多い手口や最近の社会情勢などを利用した新しい手口などさまざまなパターンがあります。
よくある手口をあらかじめ知っておくことで、詐欺被害にあうことを未然に防げるでしょう。ここではワンルームマンション経営でよく見られる5種類の詐欺について概要を紹介します。
手付金詐欺
手付金とは、不動産契約において契約の証拠として飼い主が売主に支払うお金のことで、業者に手付金を持ち逃げされる詐欺を手付金詐欺と呼びます。
「人気の物件だから早く契約したほうがいい」などと言って急かされるときは注意しましょう。手付金を払うと業者は姿を消してしまい、連絡が取れなくなるというケースがあります。悪質なケースでは、複数の人に対して同じ物件を契約したように見せかけて手付金を払わせ、持ち逃げすることもあります。
相手が宅建業者の場合で、手付金を支払うようにしつこく進めてくるならば、宅建業法に則った免許を持っているか確認しましょう。不動産売買のような仲介業を営むには都道府県知事または国土交通大臣からの免許が必要です。会社の公式Webサイトや営業担当者の名刺に宅建免許の番号の記載があることを確認しましょう。宅地建物取引業保証協会のような宅建業者だけが加入できる組織に登録しているかどうかも、信頼できる業者を見分けるポイントです。手付金は契約を前提に支払うものであり、返ってくる保証がないため、基本的に払わない心持ちでいることが大事です。
デート商法詐欺
デート商法詐欺とは、業者などが恋人を装い、親密になったところで不動産投資をすすめてくる、人の恋愛感情に付け込んだ詐欺です。
嫌われたくないという気持ちから断れず、契約すると相手と連絡が取れなくなるという手口が典型的です。中にはクーリングオフが可能な期間を過ぎてから音信不通になるという手口もあります。恋愛感情につけ込む手口からデート商法詐欺と呼ばれ、不動産投資以外でも見られます。
本名や所属などの素性を知らせなくても多くの相手と簡単に出会えるマッチングアプリが普及したことで増えている詐欺だといわれています。
二重譲渡詐欺
二重譲渡詐欺とは物件が売却済みであることを伏せて契約を結び、購入代金を払わせる詐欺のことです。
悪質なものでは一つの物件を3人以上の人に売ると見せかけてそれぞれから代金を騙し取るケースがあります。これは仲介業者の知らない間に売主が行なっているパターンと、詐欺グループとして行なっているパターンがあります。
購入代金を支払っていても、不動産の所有権を主張できるのは先に登記を済ませた人のみです。そのため、事前に登記内容の確認をしておくことが必要です。
入居状況詐欺
入居状況詐欺とは空室が目立つマンションにサクラを入居させ、一時的に満室になっているように見せかけて売却する詐欺のことです。
満室で利回りが高いことを理由に、相場よりも高い価格で物件を買わせることもあります。売買契約が成立した途端にサクラの入居者が次々と退去するため、オーナーは期待したような家賃収入を得られないおそれがあります。契約前に実際の入居者とサクラを見分けることは難しいため防ぎにくい詐欺の一つです。
そのため、レントロールで各部屋の契約時期を確認し、不自然な動きがないかを確認することが大事です。ただし、レントロールが改ざんされていたり、巧妙に入居者がいるように見せかけたりしてくることもあり、見抜くのが難しい詐欺の手口となっています。
海外不動産投資詐欺
海外不動産投資詐欺とは、海外にあり現地に確認しに行くことが困難なことを逆手にとって、存在しない物件やひどい状態の物件を購入させることです。
海外の不動産であること理由に、相場よりも高い価格での売買契約や不要な手数料を要求されるケースがあり、お金を持ち逃げされて物件も手に入らない、といったこともあり得ます。
不動産が海外にあるため簡単に物件の確認ができないことや、契約の際に英語などの言語で手続きをする必要があることに注意しましょう。また、日本のように困ったら警察・弁護士が何とかしてくれると思わないほうが良いでしょう。
マンション経営を始めるなら最初の情報収集が重要です。日本最大級の土地活用プラン比較サイトイエウール土地活用なら、土地所在地を入力するだけでマンション経営のプランを取り寄せることができます。
\最適な土地活用プランって?/
活用事例:自己管理による賃貸経営のお悩みを建て替えで解決




| エリア | 東京都 |
| 土地面積(㎡) | 490.8 |
| 延べ床面積(㎡) | 2273.82 |
| 工法 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
(大東建託株式会社の土地活用事例)
ワンルームマンション経営で注意するべきセールストーク
ワンルームマンション経営で詐欺を働こうとする、悪質な不動産会社の営業担当者が好んで使うセールストークがあります。
ワンルームマンション経営の勧誘で注意すべき誘い文句を紹介します。営業担当者からこれらの言葉を聞いたら要注意です。
「節税できる」
ワンルームマンション経営で減価償却費を計上して節税するテクニックがあるのは事実ですが、誰でも対象になるわけではありません。
節税が可能なのは年収1,200万円以上かつ築古マンションという条件を満たす場合に限られます。節税効果のない人が節税効果のない物件を購入してもメリットはなく、赤字が増えるだけなのです。
新築や築浅物件だったり、年収1,200万円未満であるのが明らかであるにもかかわらず、節税メリットをやたらとアピールする業者には注意しましょう。営業担当者がルールに詳しくないか、誤認させようとしているのかもしれません。
「急いで契約した方がいい」
「人気の物件なので、すぐに契約した方がいい」などと急かしてくる業者は要注意です。中には非常に好条件で、申込みが集中する物件もあります。
しかし、大きな金額を必要とするワンルームマンション経営は特に慎重に検討して判断を下すべきです。契約を急かしたり、急いでいるからと細かな説明を省略して契約へ進もうとしたりする業者は怪しいといえるでしょう。何か不利な情報を隠しているのかもしれません。
なお、ワンルームマンション経営は一般的にクーリングオフの対象になりません。契約後のキャンセルは費用がかかることが多い点も押さえておきましょう。
「家賃保証があるので空室でも安心」
セールストークで家賃保証と言われたらサブリース契約のことを指していると考えられます。家賃保証のサービスは条件や機関などの制限があるため、契約内容をよく理解することが大切です。あえてサブリース契約の不利な面を隠して契約させる業者には注意しましょう。
サブリースとは毎月定額の賃料を不動産会社から受け取れる契約形態です。そのため不動産投資のリスクの一つである空室リスクを回避できるメリットがあります。空室リスクは、ワンルームマンション経営の大きなリスクの一つです。そのため家賃保証に魅力を感じるオーナーは少なくありません。
一見オーナーにとって有利なシステムに思えますが、そんなことはありません。サブリース契約の注意点は、保証率は変動せず、物件状況や賃貸需要などによって賃料が下げられてしまうというところです。管理会社から払われる家賃が少なくなる可能性を意図的に隠し、永久に最初に提示された家賃が保証されるといった説明をしてくるところが、サブリースが詐欺まがいとされる所以となります。
「クーリングオフできる」
ワンルームマンション経営を含む不動産取引について定めた宅地建物取引業法(宅建法)にはクーリングオフに関する規定があります。そのため条件を満たせばマンション経営もクーリングオフできます。
ただし、クーリングオフの条件には業者の事務所以外で申込みや契約したといったものがあり、ワンルームマンション経営で当てはまるケースは少ないでしょう。
クーリングオフできない場合、キャンセルには手付金の放棄などが必要です。「クーリングオフできるのでまずは契約を」と急かしてくるのは怪しいと考えられます。
「年金代わりになる」
ワンルームマンション経営は比較的長い期間にわたって続けられる投資方法です。そのため現役中にローンを完済すれば、引退後に得られる家賃収入を年金代わりにできるというセールストークを聞くことがあるかもしれません。
ただし、ローンを完済していたとしても管理費は引き続き発生する上、修繕費などがかかるため家賃収入すべてが収入になるわけではありません。
入退去による原状回復費用や入居付けに必要な広告費、老朽化による大規模修繕費など、出費はいくらでもあります。年金代わりという言葉を鵜呑みにしないようにしましょう。
「生命保険代わりになる」
不動産投資ローンを利用する場合、団体信用生命保険に加入することが一般的です。団体生命保険とは、契約者にもしものことがあった場合にローンを代わりに返済する保険です。残された家族には物件が残るため生命保険代わりとして使えます。
ただし、投資の一つであるワンルームマンション経営にはリスクもあります。保険料を節約できる以上の損をするおそれもあるため、慎重に判断することが大切です。
「自己資金がいらない」
「自己資金がなくてもフルローンでマンション経営が始められる」というセールストークにも注意しましょう。
そもそも頭金を用意できない状態でワンルームを始めることは、ローンを返済できなくなる可能性があります。
空室が続いて家賃収入が得られなくなったときや、突発的に修繕が必要になった場合、ローンの返済すら難しくなってしまうかもしれません。ローンの返済が滞れば、最悪の場合はマンションを手放すことになります。
「手頃な価格で購入出来て儲かる」
「区分マンションは手頃な価格で購入することができて儲かる」、といったことも良く聞くセールストークです。
安いからと言ってすぐの物件を購入するのは悪手です。なぜなら、物件が安いことにはなんらかの理由があり、安くしないと売れないから安くしている、と考えるのが妥当です。
また、営業マンの中にはやたらと高利回りであることをアピールしてくる人もいます。こういった際に営業マンが使う「利回り」は「実質利回り」ではなく「表面利回り」ですので、営業マンの言う利回りを鵜呑みにしてすぐに契約へと至らないようにしましょう。
「リスクは無いから大丈夫」
営業マンの中には、「マンション経営んはリスクがないから大丈夫」というトークで陥れようとしてくる人もいます。
こういったことを言われた場合、投資に関する知識がないと相当甘く見られているか、営業マン自身に知識があまりないかのどちらかです。当然マンション経営にリスクは切っても切り離せません。
つまり、「リスクがないから購入するべき」といったことを言ってくるような営業マンを信じてはいけません。
ワンルームマンション経営で実際に合った詐欺の事例
ワンルームマンション経営の勧誘に関して、悪質な勧誘というのは一定数存在します。そして、そういった勧誘は大体詐欺・詐欺まがいのものである可能性が高いです。
本章では。実際に合った詐欺の事例や、自治体に寄せられた相談事例について紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
デート商法詐欺の事例
SNSや婚活サイトなどで知り合った異性から、投資用マンションの購入を勧められて契約をしてしまった、という相談が各都道府県の相談窓口に寄せられることも少なくありません。
「節税対策になる」「二人の将来のため」という言葉で騙され、投資用マンションを購入してしまうというパターンが多いです。このデート商法詐欺について、東京都の消費生活総合センターに寄せられた相談事例を紹介します。
参考:東京都ホームページ
相談事例①
相談事例②
相談事例③
つい話を聞いてしまうことにより詐欺にあうケース
業者がアンケートなどを利用して目的をはっきり述べずに話が始まり、結局マンションの購入を断れずに契約をしてしまう、ということも多々あります。
話にメリットや魅力を感じてしまうことが要因の一つです。埼玉県の消費生活支援センターに寄せられた相談事例を紹介します。
参照:埼玉県ホームページ
相談事例①
次に、売主である不動産業者と売買契約の手続をすることとなったが、不安になり契約は取りやめたいと申し出たが聞き入れてもらえなかった。後日、不動産業者と2,500万円の中古マンションの購入契約をしたが、高額なので解除したい。
相談事例②
翌日は上司と二人で来訪し、マンション購入の話になった。断っても「社会人としてどうなのか。」など説教され、物件の内見も断れず行くことになった。内見に向かう途中でATMに連れて行かれ、50万円を用意するように言われた。契約の意思がないことを伝えたが、深夜まで拘束され、疲れ果ててやむなく契約した。不本意な契約なので解除したい。
架空の開発計画で土地の売買契約の勧誘を行っていた事例
北海道ではとある事業者が、開発計画を進めているという嘘で土地の価格が上がると消費者に伝えて売買契約を勧めたり、売買契約の内容を明らかにする書面にクーリングオフに関する事項を記載しなかったりといった違反行為を行なった事例があります。
それについて、実際に詐欺の被害にあった人がどういった経緯で騙されてしまったかをいくつか事例で紹介します。
事例①
事例②
事例③
知らぬ間に詐欺を行なっているケースとその事例
不動産業者から詐欺を受けるパターンだけではなく、知らない間に自分が詐欺の片棒を担がされているケースもあります。
本章では、知らぬ間に詐欺を行なってしまっているケースとその事例について紹介します。
二重売買契約
二重売買契約とは、実際の契約書と金融機関用の契約書の2通を用意し、金融機関には実際の売買価格よりも高い金額を記載して提出することです。これにより、本来よりも多くの融資を引き出すことができてしまいます。
例え自分は知らなかったとしても、押印をしてしまった時点で偽造の契約書作成に加担したとみなされても文句は言えません。偽造した書類を金融機関に提出することはもちろん問題であり、そのことが金融機関に知られた場合、ローンの一括返済を求められる可能性があります。
また、二重売買契約によって借入額が増えるため、その分毎月の返済額も増えてしまうという問題点もあります。そのため勧誘の言葉を鵜呑みにせず、契約書などの書類は自分自身で慎重に確認することが大切です。
事例
不動産投資サイト健美家による、リーマン大家が二重売買契約で物件を購入して犯罪の片棒を担いでしまった、という事例を紹介します。
エビデンス改ざん
エビデンス改ざんとは、ローン審査時に所得証明の源泉徴収票や通帳残高などを偽装して金額を改ざんして提出し、ローンを通過させるという手口です。
これについても、知らなかったとしても文書偽造の罪に問われる可能性や、金融機関からローンの一括返済を求められることがあります。また、本来なら融資を受けられないはずの与信力で物件を購入するため、想定外の出費が続いた場合、家賃収入や給与収入でまかなえず破綻してしまう可能性があります。
そのため、不動産業者から担当の銀行員を紹介してもらい、自分が不動産業者に提出した書類の内容に違いがないかを確認しつつ審査を進めることをおすすめします。
事例
不動産投資サイト健美家による、知らぬ間にエビデンス改ざんに加担してしまっていた大家についての事例を紹介します。
1法人1物件スキーム
1法人1物件スキームとは、投資物件を購入する際に新設法人を作り、複数の金融機関から融資を受ける方法です。多法人スキームや複数法人スキームとも呼ばれます。
投資家本人は連帯保証人として設定されますが、個人信用情報は融資に関する記載されないため、新設法人ごとに融資を受けることができるという仕組みです。そのため、不動産投資事業を短期間で拡大する方法として注目を集めていました。
この手法を悪気なく利用しているオーナーも多いですが、金融機関に借入を報告しないことは詐称行為となるため、この手口を知られてしまった場合はローンの一括返済などを求められるリスクがあります。
ワンルームマンション経営で詐欺を回避するために
ワンルームマンション経営で詐欺にあわないためには怪しい業者や物件を見抜くことが大切です。
不動産投資の知識をつける
ワンルームマンション経営を含む不動産投資で詐欺が起こる理由の一つに情報の非対称性があります。情報の非対称性とは、売り手と買い手が持つ情報量や質にギャップがあることです。
買い手が不動産投資の知識をつけることで、両者のギャップを埋められます。業者の説明を鵜呑みにしなくなり、説明のおかしな点に気づけるようになるでしょう。
ある程度の不動産投資の知識をつけることは、詐欺から身を守ることにつながります。
分からないことがあるときは投資しない
不動産業者の説明を聞いていて、納得できない場合や理解できない点がある場合は投資しないことが大切です。
ワンルームマンション経営は比較的大きなお金が必要になる上、一度始めると数十年にわたって続くこともある投資方法です。疑問点を抱えたまま投資をすることはおすすめできません。
不明点があるときは契約を結ぶ前に営業担当者へ積極的に質問しましょう。その答え方も、信頼できる業者を見抜くポイントです。答えをはぐらかすような業者は怪しいかもしれません。
不動産会社が信頼できるかどうかを見極める
マンション経営の勧誘で詐欺なのかどうかに迷ったときは、その会社が信用に値するのかを見極めましょう。
信頼できるかどうかは、提案力があるか・対応は丁寧か・資本金はどれくらいか・設立してからどれくらい経つかなどの経営状態を考慮して判断しましょう。
また、実際に事務所の足を運び、社内の雰囲気を肌で感じることもおすすめです。怪しい業者の事務所にはどことなく不穏な空気を感じることでしょう。
ワンルームマンション経営で詐欺にあってしまった場合
ワンルームマンション経営の詐欺の手口が巧妙で、気づかずに契約してしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
また、実際にワンルームマンション経営が始まってから詐欺だと分かることもあります。詐欺かもしれないと気づいたときの対処法を解説します。
公的機関や不動産協会に相談する
ワンルームマンション経営を契約後に詐欺かもしれないと気づいたら宅地建物取引業保証協会、消費生活センター(国民生活センターなど)、国土交通省などに相談しましょう。公正な立場から相談に乗り、アドバイスをしてもらえます。
特に宅地建物取引業保証協会は、所属する不動産会社による取引で発生した債権の一部または全部を弁済してくれる可能性もあります。
また、悪質な勧誘を受けた場合は国土交通省へ連絡するのがおすすめです。悪質な不動産会社に対して営業停止や免許取り消しなどの厳しい行政処分を下すこともあります。
弁護士に相談する
詐欺にあったが相手の不動産会社がキャンセルに応じてくれないといった法律トラブルは弁護士に相談するのがおすすめです。内容や状況に応じて適切な対処方法を教えてもらえるでしょう。
なお、弁護士にはそれぞれ専門分野があります。ワンルームマンション経営に関するトラブルについて、どの弁護士に依頼すべきか分からない場合や費用の面で不安がある場合は法テラス(日本司法支援センター)を利用するのも方法の一つです。
早期売却で被害を抑える
詐欺だと気づいたらできる限り早くマンションを売却した方が損失を抑えられる可能性があります。無理にマンション経営を続けることで損失が拡大するかもしれません。
ただし、市場環境によっては少し待ってから売却する方がよい場合もあるため、まずは査定してもらい、マンションの市場価値を把握するのがおすすめです。
まとめ
ワンルームマンション経営に関する詐欺には手付金詐欺やサブリース詐欺など、いくつかのパターンがあります。
詐欺のパターンや注意した方がよいセールストークを押さえることで、詐欺の被害を防ぎましょう。また、不動産投資の知識をつけることも効果的です。
中には悪質な業者もあるとはいえ、ワンルームマンション経営は安定した収入が得られる魅力的な投資方法です。この記事を参考に、信頼できる業者を見つけてワンルームマンション経営を始めてみましょう。