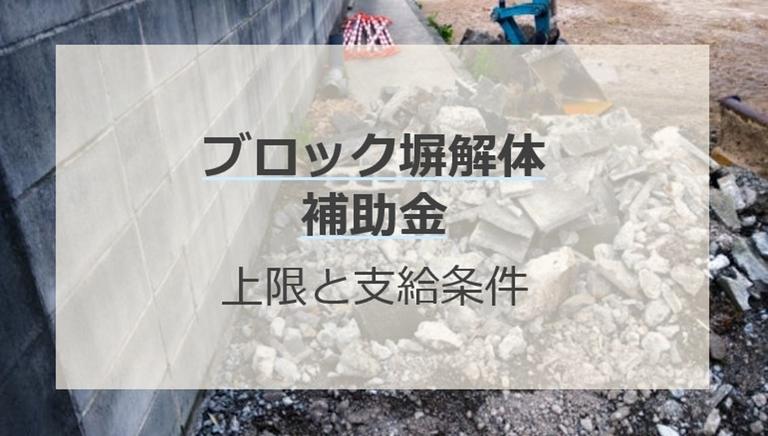「ブロック塀の解体で補助金は使える?」
ブロック塀を解体する場合、自治体によっては補助金制度を利用できる可能性があります。
支給額も自治体によって異なりますが、相場は撤去費用の1/4~1/2かつ上限額が5万円~15万円となっています。
ブロック塀解体の補助金制度は「倒壊の危険性があるブロック塀を除却し、地域の安全を守ること」が目的とされています。よって、支給条件も「一定の高さがある」「ブロック塀に亀裂が入っている」等が該当するケースが多いです。
本記事ではブロック塀の解体で利用できる補助金制度の申請条件や支給額、申請手順について解説しています。
私の家の解体費用はいくら?
▼解体費用の基礎知識について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
ブロック塀の補助金は地震による倒壊防止が目的
ブロック塀の補助金は地震による倒壊防止が目的です。
その後、多くの自治体で補助金が出されるようになり、調査、撤去、改修、付け替えが対象となっています。
なお、金額は自治体ごとに異なるため、各自治体のホームページで確認しましょう。
私の家の解体費用はいくら?
解体補助金の対象となるブロック塀
ブロック塀解体補助金の対象となるのは、次のブロック塀です。
▼解体補助金の対象となるブロック塀
- 地震時に倒壊の危険性がある
- 道路に面する
- フェンスや生垣の設置が目的で解体される
以降で詳細を解説しています。
地震時に倒壊の危険性があるブロック塀
地震の際に倒壊する可能性があるブロック塀の特徴は、主に次の7つです。
▼地震の際に倒壊する可能性があるブロック塀の特徴
- 1.2m以上の高さがあるブロック塀
- 高さに対して厚みがないブロック塀
- 劣化によるひび割れがあるブロック塀
- 傾きがあるブロック塀
- 築30年以上経過したブロック塀
- 鉄筋が通っていないブロック塀
- コンクリートの基礎工事がないブロック塀
詳しく説明します。
特徴①1.2m以上の高さがあるブロック塀
高さが1.2m以上のブロック塀は倒壊の危険があるため、解体を検討すべきです。理想の高さは1.2m以下で、それ以上は倒壊リスクが高まります。法律では2.2mまでと定められており、それを超えると違法でさらに危険です。1.2m以上の場合、控え壁の設置も検討してください。
特徴②高さに対して厚みがないブロック塀
特徴③劣化によるひび割れがみられるブロック塀
特徴④傾きがあるブロック塀
傾きがあるブロック塀は倒壊の危険が高いです。劣化の兆候であり、特に基礎部分に傾きがあると、小さな刺激で崩れる可能性があります。地震や雨、車の振動などでも倒壊するおそれがあるため、注意が必要です。
特徴⑤築30年以上経過したブロック塀
特徴⑥鉄筋が通っていないブロック塀
鉄筋が通っていないブロック塀も崩れる危険性があります。建築基準法では、ブロック塀には太さ9mm以上の鉄筋を80cm以下の間隔で縦横に配置することが求められています。
ただし、1950年以前のものや施工が不十分なものは、この基準を満たしていない可能性があります。外観からは判断が難しいため、倒壊のリスクがある場合は点検を依頼することをおススメします。
特徴⑦コンクリートの基礎工事がないブロック塀
道路に面するブロック塀
補助金は道路に面するブロック塀も対象になります。
道路に面する場合は倒壊すると事故に発展する可能性が高いためです。避難路や通学路、一般道に面していて、かつ倒壊の危険性がある場合が対象です。
フェンスや生垣の設置が目的で解体されるブロック塀
フェンスや生垣の設置が目的で解体される場合も、補助金の対象になります。
ブロック塀解体補助金の支給額
ブロック塀解体の支給額は解体費用の1/4~1/2かつ上限額5万円~15万円が相場です。例えば、解体工事費用が13万円~26万円の場合、3万円~12万円(解体工事費用に1/4~1/2を乗じて算出)の補助金を利用できることになります。
ただし、補助金制度は自治体によって異なるため、支給額ももちろん自治体ごとでバラつきがあります。以下は自治体別の支給額の事例です。あくまで自治体によって金額が異なる点に注意してください。
▼ブロック塀の解体補助金の事例
| 自治体 | 支給額 |
| 東京都船橋市 |
|
| 茨城県河内町 |
|
| 愛知県名古屋市 |
|
| 佐賀県みやき町 |
|
| 熊本県熊本市 |
|
※各自治体の名称から、自治体の補助金制度の公式ホームページを閲覧できます。
私の家の解体費用はいくら?
ブロック塀解体補助金の申請から給付までの流れ
▼ブロック塀解体補助金の申請から給付までの流れ
- 【施主】自治体窓口で相談
- 【自治体】現地調査で補助の可否を審査
- 【施主】見積もりを取得・補助金の交付
- 【自治体】補助金交付の決定
- 【施主】解体工事の実施・実績の報告
- 【自治体】補助金額の確定・給付
参考|東京都船橋市 危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業に係る手続きフロー図
STEP①【施主】自治体窓口で相談
まずは解体したいブロック塀が位置するエリアを管轄する自治体の建築指導課の窓口に相談しましょう。
窓口に相談すると、補助金制度の有無や、申請条件に関する詳細、申請に必要な書類や手続きの流れについて職員から説明をうけることができます。
また、補助金制度に関する詳しい情報は各自治体の公式ホームページからも確認できます。相談前にひととおり内容をチェックしておくと、話がスムーズに進みます。
STEP②【自治体】現地調査で補助の可否を審査
自治体に補助金制度がある場合、利用を希望することで、自治体から現地調査をうけることができます。
現地調査では、自治体の職員がブロック塀を実際に確認し、補助金の支給対象であるかチェックを行います。
現地調査によって、自治体から支給対象と判断された場合のみ、補助金を申請できる点に注意しましょう。
STEP③【施主】見積もりを取得・補助金の交付
現地調査で補助が可能と判断されたら、自治体が交付金額を決められるように、解体工事費用の見積もりを取得します。
解体工事費用の見積もりは、解体業者に現地調査を依頼することで取得が可能です。
できるだけ安い費用で解体したい場合は、少なくとも2~3社に依頼して、見積もり金額を比べることがおススメです。
解体費用の見積もり書類を取得したら、そのなかから一つを選び、自治体に書類を提出して、補助金の交付申請を行いましょう。
STEP④【自治体】補助金交付の決定
自治体は解体費用の見積もり金額を元に、改めて審査を行い、補助金交付を正式に決定します。
審査には数週間から数カ月かかる場合もあるので、余裕をもってスケジュールを組んでおきましょう。
STEP⑤【施主】解体工事の実施・実績の報告
補助金交付が決定したら、施主は解体工事を実施し、実績の報告(=解体費用の領収書の提出)を行います。
STEP⑥【自治体】補助金額の確定・給付
自治体は報告された実績をもとに、補助金額の確定と給付を行います。
内容に問題がなければ指定の口座に補助金が振り込まれます。
私の家の解体費用はいくら?