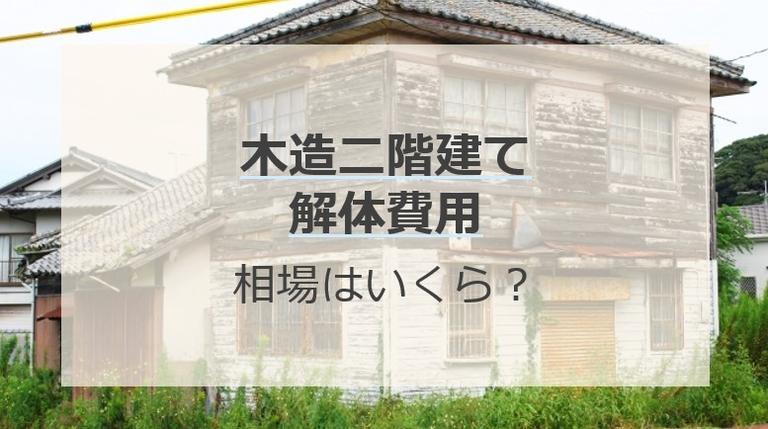木造二階建ての家を解体する場合、家の規模や立地条件によって相場は異なりますが、一般的に100万円以上の解体費用が必要となります。
本記事では、木造二階建ての解体工事を具体的にご検討中の方に向けて、費用の相場と内訳、工事の流れ、費用を決める要因、削減するコツなどをご紹介します。
▼家の解体費用の相場についてはこちらの記事でも詳しく解説しています
木造二階建ての解体費用の相場
木造二階建ての家を解体する場合、大まかな解体費用は坪単価に延べ床面積を掛けることで計算できます。
たとえば、坪単価3万円、延べ床面積が30坪の場合、「3万円 × 30坪 = 90万円」が解体費用の目安です。
なお、木造の家の坪単価は3万円〜4万円が相場で、坪数別の費用は以下が目安となっています。
▼坪数別の解体費用の相場
| 坪数 | 木造二階建ての費用の目安 |
| 20坪 | 60万円~100万円 |
| 30坪 | 90万円〜120万円 |
| 50坪 | 150万円~200万円 |
私の家の解体費用はいくら?
鉄骨造やRC造よりも割安な傾向
家の解体費用の坪単価は、鉄骨造で3万円〜8万円、RC造で5万円〜9万円が相場となっています。
木造の解体費用が割安となる理由は、解体に掛かる労力が少なく、処分費用が高額となる廃材が発生しないことによります。
ただし、ツーバイフォー工法など、耐久性の高い工法を使用した築浅の木造二階建ては、解体費用が高額になる可能性があるためご注意ください。
延べ床面積で計算する点に注意
坪単価を使った解体費用の計算は、建築面積(建坪)ではなく、一階部分と二階部分を合計した延べ床面積を使用します。
そのため建坪30坪の平家よりも、建坪30坪の二階建ての方が解体費用が高額になる点に注意しましょう。
地下室がある場合や、ブロック塀・カーポートなどの撤去工事を必要とする場合にも、解体費用は高額になる可能性があります。
私の家の解体費用はいくら?
木造二階建ての解体費用の内訳
木造二階建ての解体工事では、建物の解体だけでなく、付帯物の撤去や廃材の処分、整地等の工程ごとに費用がかかります。本章では、木造二階建ての解体費用の内訳として、以下の6つの費用項目を解説しています。
▼木造二階建ての解体費用の内訳
- 仮設工事費用
- 解体工事費用
- 付帯工事費用
- 廃棄物の処分費用
- 整地費用
- 諸経費
それぞれ詳しく紹介します。
仮設工事費用
仮設工事費用は養生費と呼ばれることもあり、現場の養生や足場の組み立てなどに必要な費用を指します。
近隣への影響を防ぐための防音・防震防塵シートの設置の他、仮設トイレ、工事用の水道・電気の設置費用も含まれています。
解体工事費用
解体工事費用は、木造二階建ての家自体を解体するために掛かる費用です。前述の通り、坪単価と延べ床面積で計算されます。
なお、解体工事費用は、現場作業員に対する人件費が大半を占めています。よって、天候や立地の都合で工期が延びてしまうと高額になってしまう点に注意です。
私の家の解体費用はいくら?
付帯工事費用
付帯工事費用とは、敷地内にある駐車場や井戸、庭木などの撤去に必要な費用を指します。
以下は、付帯物の種類別の撤去費用の相場です。数が多い場合や工事面積が広い場合には、値引き交渉に応じてもらえる可能性もあります。
| 費用の種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| カーポート撤去費用 | 6万円~/1台用 |
| ブロック塀撤去費用 | 5,000円~1万円/1㎡ |
| 植物の撤去費用 | 5,000円~3万円 |
| 門扉の撤去費用 | 2万円程度 |
| 倉庫・物置の撤去費用 | 2万円~3万円 |
| 浄化槽の撤去費用 | 5万円〜10万円 |
| 井戸の埋め戻し費用 | 3万円〜5万円 |
| アスベストの撤去費用 | 2万円〜8.5万円/1㎡(300㎡以下) |
廃棄物の処分費用
廃棄物の処分費用は、解体工事に伴って排出される廃材を運搬・処分するための費用です。
以下のように、金額は廃材の種類ごとで計算されます。
| 廃材の種類 | 処分費用(㎥あたり) |
|---|---|
| コンクリートガラ(コンクリートのがれき) | 5,000円~ |
| タイル・ガラス | 2万5,000円~ |
| 石膏ボード | 1万5,000円~ |
| 木くず | 5,000円~(都道府県によって異なります) |
整地費用
整地費用は、解体後の土地を整備・舗装するための費用です。
土地の売却・転用を考えている場合には、整地にコストを掛けた方が有利になる可能性も高まります。
費用相場は1平米あたり1,000円程度ですが、土地が傾斜している場合は金額が高くなりやすいです。
諸経費
諸経費には、工事車両の駐車料金や、公的機関への届出・手続きの代行手数料、近隣へのあいさつに持参する手土産の費用などが含まれます。
諸経費の金額や内訳は、解体業者によって大きく異なるため、見積もりの際に明細について問い合わせておくと安心です。
私の家の解体費用はいくら?
木造二階建ての解体工事の流れ
木造二階建ての解体工事は、一般的に以下の流れで進めることとなります。
なお、家の解体工事に必要な期間は、約2週間が目安です。ただし、付帯工事の量が多い、悪天候により工事が延期する、地中埋設物が見つかる等の追加工事が発生する場合、1ヶ月以上の工期を要する場合もあります。
- 見積もり・業者選び
- 事前準備
- 解体工事
- 解体に伴う廃材の処分
- 整地
見積もり・業者選び
まずは解体費用の見積もりを複数の業者に依頼し、それを基に業者を決定します。
見積もり・業者選びは以下の手順で進みます。
業者へ連絡する
一口に解体業者と言っても、木造の解体が得意な業者や鉄骨造の解体が得意な業者、またはマンションの解体が得意な業者や戸建ての解体が得意な業者など、それぞれ経験の違いや得手不得手が存在します。
よって、木造二階建ての解体実績が豊富な業者を選出するようにしましょう。依頼する際は、解体費用の相場や工期、どういった業者に依頼すべきか等の情報収集をあらかじめ行なっておくことをおススメします。
現場調査をする
解体業者を決める段階で現場の調査も行ないます。主な調査は解体する建物の構造や広さ、周辺状況、アスベストの有無などです。
建物にアスベストが使用されていた場合は、解体前に除去工事を行います、アスベストの除去は専門の業者にしか行なえないため、解体業者の指示に従い除去業者を確保しましょう。ただし、発じん性が著しく低いアスベストと判断された場合、解体業者でも撤去することができます。
相見積もりをする
現場の調査が終わったら見積もりを出してもらいます。見積書という形で書面にて金額を提示してもらうことが重要で、その際項目ごとに費用を記載して貰うようにしましょう。
見積もりの金額に関して、解体工事にかかる費用のみではなく、その他にかかる費用全てを合計した金額を提示してもらい、その最終的な見積もりで複数の業者を比較検討するのがおすすめです。
業者を決定する
業者の決定をする際は、金額だけではなくその業者の対応の良さや実績なども考慮して判断することが大事です。
見積もりでは安く提示しておき、後々多額の追加費用を請求してきたり、廃材の処分を適切に行わなかったりなどといった業者も存在するため、業者選びは総合的に判断して決めるようしましょう。
私の家の解体費用はいくら?
事前準備
解体業者が決まったら工事を行なうための事前準備に入ります。
解体工事の事前準備では、電気・ガスを停止し、電話線などを撤去しておきます。
また、クレームやトラブルを避けるためにも、事前に挨拶をしておくことが重要です。解体工事が始まると、騒音・振動や埃の飛散などで近隣住民へ迷惑をかけることになるためです。その際、施主として業者に同行することをおススメします。
また、解体工事の前には残置物の撤去も行ないます。室内に粗大ごみや家電製品などが残っている場合、撤去に追加費用が取られるため、工事前にごみ処理業者へ依頼したり、リサイクルショップに出したりなどして整理しておきましょう。
解体工事
事前準備がすんだら、いよいよ解体工事です。
解体工事は「付帯物の撤去➡足場・養生の組み立て➡建物内部の解体➡建物本体の解体」といった順にすすみます。
外構や庭木、庭石などの付帯物は建物の解体前に撤去します。その後、足場と養生を組み立てた後で、建物の解体工事を行います。建物の解体は、内部から作業していくます。天井や床をはがして撤去し、その後建物本体を解体していきます。
解体に伴う廃材の処分
建物の解体によってごみや木材やコンクリートなどの廃材が多く発生するため、それらの撤去を行ないます。
鉄くずなどのリサイクル可能な資源と、処分が必要な廃材は分別して業者によって搬出されます。
整地
廃材の処分が済んだら土地の整備を行ないます。地中の埋設物の有無を確認し、土地を平らにする整地作業をします。
問題がなければ解体工事は終了となりますが、古い建物の基礎などの地中埋設物が発見された場合は、撤去工事を追加で行います。
木造の解体費用を決める要因
解体費用の相場は木造だと坪単価が3万円~4万円ですが、実際はいくつかの要因によって変動します。
ご自宅の場合に該当しないか、本章で確認してみてください。
▼木造の解体費用を決める要因
- 立地・地域
- 解体業者
- 建築物の大きさ
- 特殊な工事の発生
立地・地域
立地や地域によっても解体にかかる費用が変わります。
間口の広さが5mに満たなかったり道路の幅が狭かったりして、重機が入れないような立地の場合、手作業での解体が増えるため工事費が高くなります。
また、工事現場が住宅街の中である場合も、騒音規制法に基づき防音対策が必要になり、手作業が増えたり解体期間が延びたりして、工事費が高くなってしまいます。
解体業者
同じ工事の内容だったとしても、解体業者によって費用が異なることが多くあります。
業者ごとに利益率の設定が異なることや、拠点から現場までの距離も異なることが原因です。また、解体業者の人手不足や、解体作業の長期化によるところもあります。
私の家の解体費用はいくら?
建築物の大きさ
解体費用の相場は、建築物の大きさによっても異なります。
建築物が大きい建物ほど、廃棄物も多く、廃材処分費用も高くなるためです。
特殊な工事の発生
アスベストの除去や地中埋設物の撤去などの特殊な工事が発生する場合、解体費用が高くなります。
アスベストに関しては、建材として使用が禁止となった2006年以前に建てられた建物には注意しましょう。なお、処分費用は除去作業の危険度によっても変わりますので、解体業者に現地調査を依頼して金額を見積もってもらいましょう。
地中埋設物に関しては、撤去費用は埋設物の種類や量によって異なります。埋設物については建物を解体してみないとわからないため、見積もりに含ませることはできない点に注意しましょう。
私の家の解体費用はいくら?
木造二階建ての解体費用を相場より安く抑えるコツ
木造二階建ての解体費用の目安は、30坪の場合で120万円が相場です。そこに廃棄物の処分費用や付帯工事費用が上乗せされ、100万円以上の費用を要するケースも少なくありません。
本章では、高額な解体費用を安く抑えるための方法として、以下の5つをご紹介します。
▼木造二階建ての解体費用を安くおさえるコツ
- 複数の解体業者から相見積もりを取る
- 家財道具や植物を処分する
- 繁忙期を避ける
- 自分で建物滅失登記を行う
- 自治体の補助金・ローンを使う
複数の会社から相見積もりを取る
解体費用の見積もりを取る際には、1社ではなく、複数の会社に依頼することが大切です。
1社の見積もりだけで解体工事を進めてしまうと、相場より割高な費用を支払ってしまう可能性が高くなります。
また、複数の解体業者に相見積もりを依頼することで、相場観がわかり、価格交渉の際の判断材料にもなります。
金額だけで解体業者を選ぶのではなく、問い合わせへの対応や見積もりのわかりやすさなどを考慮して決めると安心です。
家財道具や植物を処分する
解体する木造二階建ての家の中に不用品が残っている場合、事前に処分しておくことで費用削減につながります。
解体工事に伴う廃棄物は「産業廃棄物」として扱われ、家庭ごみや粗大ごみよりも処分費用は高額となります。
そのため解体する家は可能な限り空にしておき、庭木なども撤去しておくことで解体費用を安く抑えることが可能です。
繁忙期を避ける
年末・年度末の繁忙期は解体費用が割高になる傾向にあります。
一方で、5月〜10月ごろの閑散期は、解体費用の見積もりが割安になりやすい時期です。
スケジュールに余裕がある場合には、これらの時期に解体工事を進めることをお勧めします。
自分で建物滅失登記を行う
家の解体が完了すると、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。
建物滅失登記は土地家屋調査士などの専門家に依頼することも可能ですが、手数料として約5万円の費用がかかります。
一方でご自身で行う場合、書類の取得費用の約1,000円で手続きできるため、費用削減のためにご自身で建物滅失登記を行うと良いでしょう。
自治体の補助金・ローンを使う
お住まいの自治体によっては、老朽化した空き家や耐震性不足の木造住宅に対し、解体費用を一部助成していることがあります。
また、地方銀行・信用金庫の中には「空き家解体ローン」を用意しているところもあります。
補助金・ローンを利用することで解体費用の負担を軽減できるため、それぞれの窓口に問い合わせるか、解体業者に相談してみると良いでしょう。
▼解体費用を安くおさえるコツについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
木造二階建ての解体工事における注意点
最後に、木造二階建ての解体工事を進める際の注意点として、以下の3つを解説しましょう。
▼木造二階建ての解体工事における注意点
- 建物滅失登記は1ヶ月以内に申請を
- 固定資産税は最大6倍に上昇
- 再建築不可物件だと新しく建物が建てられない
それぞれ詳しくご紹介します。
建物滅失登記は1ヶ月以内に申請を
前述した建物滅失登記をご自身で行う場合には、家の解体後1ヶ月以内に手続きが必要な点に注意しましょう。
建物滅失登記には、解体業者が発行する解体証明書などの書類を用意する必要もあります。
最寄りの法務局まで距離がある場合や、解体工事前後のスケジュールに余裕がない場合には、可能な限り早めに登記の準備を進めておきましょう。
固定資産税は最大6倍に上昇
住宅が建っていた土地を更地にすることで、土地の固定資産税が最大6倍に上昇する点にも注意が必要です。
土地の固定資産税の計算では、「住宅用地の特例」により、家が建っている場合に固定資産税が最大1/6に軽減される仕組みがあります。
更地にすることで住宅用地の特例が受けられなくなり、固定資産税の負担が大きくなるため、更地のまま所有し続ける予定がある場合にはご注意してください。
再建築不可物件に注意
接道義務を満たさない(=幅4m以上の道路に2m以上接していない)物件は、「再建築不可物件」として解体後の家の再建築が不可能となります。
再建築不可の土地は、解体後に更地として土地を売却する場合に買い手がつきにくく売却価格も下落する傾向にあります。
家の解体にあたっては、このようにいくつかの注意点があります。そのため、解体で後悔しないためには、入念な情報収集などが必要不可欠です。
私の家の解体費用はいくら?
木造二階建ての解体費用は100万円以上掛かることも多い
木造二階建ての解体費用は、坪単価3万円、約120万円が相場です。
建物を解体するときには、アスベストの調査が義務付けられているため、アスベスト分析調査が完了してから、相見積もりを取るようにしましょう。実際、アスベストの有無で100万円程金額が変わることから、先にアスベストの調査を行うことをおすすめします。
また、解体費用を安く抑えるためには、複数の業者からの相見積もりを取り、事前に不用品を処分しておくなどの方法が効果的です。更地にすることで固定資産税が増加するほか、再建築不可物件に注意が必要な点も押さえておきましょう。
私の家の解体費用はいくら?
監修者への質問
- 解体時の隣人への挨拶は業者に任せても平気ですか?
しかし、隣家様との共有ブロック塀の撤去がある場合、養生足場を隣家様の敷地に設置させて頂く場合など、近隣の方にご協力いただく必要がある場合の工事内容ですと同行をお願いする場合もあります。
また、弊社では火災などの場合、手土産などをお持ちして挨拶させて頂きます。
- こちらに不備がないのに解体工事の期間が延びてしまった場合、別途で解体費用を請求されますか?また、その場合は払わなくてもいいですか?
もし、施工中の解体業者にそのような請求があった場合は一度契約書を確認して、内容に沿って業者との打合せが必要になると思います。
監修者:フローレス建設株式会社 伊藤誉弘さん