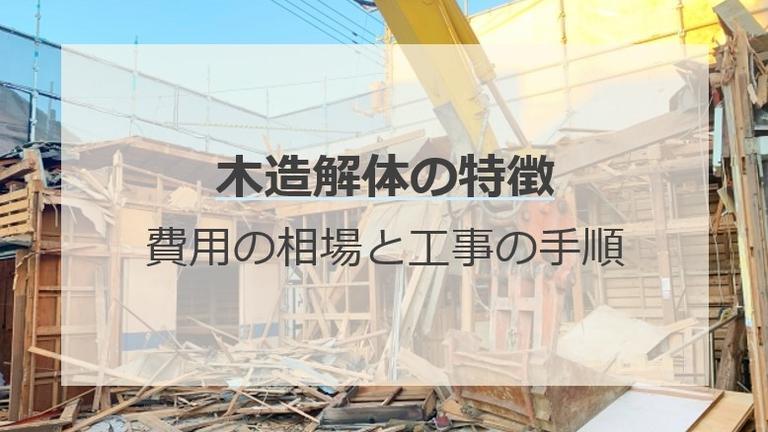「木造解体の特徴について知りたい!他の構造とどう違うの?」
長く住んでいた家が木造住宅で、相続をきっかけに解体を検討する方がいるかもしれません。木造住宅の場合、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べると分断しやすく解体費用は安くなる傾向があります。
ただし、内装材や外壁などの付帯物が多い木造住宅の場合は、分別解体が必要なため、解体費用が高くなりやすいです。
本記事では木造住宅を解体するうえでの基礎知識と解体工事の手順について、初めての方にもわかりやすく解説しています。
- 木造解体の特徴を知りたい
- 木造解体費用の相場を知りたい
- 木造解体の手順を知りたい
私の家の解体費用はいくら?
木造解体の特徴
▼木造解体の特徴
- 坪単価が比較的安い
- 付帯物の多さや立地によって高くなる可能性も
- 重機が入りづらい立地だと費用が高くなる
- 人件費や処分費の高騰に影響をうける
特徴①坪単価が比較的安い
木造住宅の特徴として、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べると坪単価が安い点があげられます。手作業で分断しやすい建材のため、解体にかかる時間が少なく費用をおさえることができるためです。
▼構造別の坪単価
| 構造 | 特徴 | 坪単価 |
|---|---|---|
| 木造 | 手壊しで分断しやすい | 3万円~4万円 |
| 鉄骨造 | 分断に工具や機材が必要 | 6万円~7万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 分断に特殊な工具や機材が必要 | 7万円~8万円 |
私の家の解体費用はいくら?
特徴②付帯物が多いと費用が高くなる
建物の解体では、付帯物の多さから相場より解体費用が高くなる可能性があります。
付帯物とは、軒天、破風板、鼻隠し、雨樋、換気フードや水切りなど、建物に設置されている設備や装飾材のことです。
付帯物は建物を解体する前にすべて手作業で撤去されます。よって、付帯物が多いほど撤去に時間がかかって工期が伸び、解体作業員に充てられる人件費(日当)が上昇し、解体工事費用も高くなります。
- ひとつずつ資材を分別して撤去するから作業負担も大きいんだよ!
資材を分別しながら撤去する方法は「分別解体」といわれ、建設リサイクル法によって実施が義務付けられています。
【分別解体とは】
建設資材廃棄物を種類ごとに分別しつつ、当該工事を計画的に施工する行為と定義しており、現場で分別しつつ解体工事を行うことは必須である。
特徴③重機が入りづらい立地だと費用が高くなる
木造住宅が重機が入りづらい立地に位置している場合も解体費用が高くなります。
- 重機が入りづらいと手作業が増えて、工期が伸びることで人件費が追加されるよ
重機が入りづらい立地としては次のような特徴があります。
▼重機が入りづらい立地の特徴
- 前面道路の道幅が4m未満で狭い
- 隣接地との距離が1m未満と狭い
- 重機を駐車するスペースが近隣に存在しない
- 前面道路における人の往来が激しい
木造の解体工事では付帯物を手作業で撤去した後で、建物本体を重機で一気に取り壊す流れが一般的です。よって、重機が使用できないと建物本体の解体も手作業で行うこととなり、解体費用が高くなりやすいので注意です。
特徴④人件費や処分費の高騰に影響をうける
解体工事の費用は人件費や処分費用の高騰によって左右されます。
昨今は空き家問題の深刻化に伴い、解体工事の案件数は増加しています。しかし、少子高齢化によって現場作業員の数は減少し、解体業界は慢性的な人手不足に陥っています。また、工事件数の増加に産業廃棄物処理場の数が追いついておらず、廃棄物処理費用の金額も高騰しています。
- 今後ますます解体費用が高騰する可能性があるから、早めの取り壊しがおススメだね
私の家の解体費用はいくら?
木造の解体費用はいくら?
- 木造解体の特徴はわかったけど、実際の費用はいくらなんだろう?
解体工事を検討するにあたって費用は最も気になる点だと思います。
そこで本章では木造解体にかかる費用の相場をより具体的に解説しています。
延べ床面積別の解体費用の相場
以下は解体費用見積一括サービスのイエウールが取得した見積事例を参考にした、解体費用の坪単価と相場になります。
▼延べ床面積ごとの解体費用の相場
| 延べ床面積 | 坪単価 | 解体費用の総額 |
|---|---|---|
| 坪単価 | 3万円 | – |
| 10坪未満 | 5.5万円 | 55万円 |
| 20坪 | 3.2万円 | 64万円 |
| 30坪 | 3万円 | 90万円 |
| 40坪 | 2.8万円 | 112万円 |
| 50坪 | 2.8万円 | 140万円 |
| 60坪 | 2.7万円 | 162万円 |
| 70坪 | 2.5万円 | 175万円 |
※一括見積依頼サービスイエウールが2023年7月に取得した見積実績を参考
- 延べ床面積の大きさにもよるけど、おおむね100万前後~200万前後と考えたらいいね
一般的に、延べ床面積が大きくなるにつれて坪単価は安くなります。解体費用の大半は解体作業員の人件費が占めますが、延べ床面積が広いとひとりあたりの人件費が分散されるためです。
私の家の解体費用はいくら?
追加費用が100万円以上上乗せされる場合も
100万円~200万円前後は建物自体の解体費用の目安ですが、追加費用が発生する場合、総額はさらに高くなります。
追加費用の内訳としては、以下があげられます。
▼木造解体で発生する追加費用
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 付帯工事費用 | 付帯物を撤去するための費用 |
| 残置物処分費用 | 残置物を廃棄するための費用 |
| アスベスト除去費用 | アスベスト除去するための費用 |
| 地中埋設物除去費用 | 地中埋設物を除去するための費用 |
付帯物や残置物、アスベストや地中埋設物が多い建物や土地であるほど、追加費用は多く発生します。
付帯物や残置物は自分でできる限り除去することで費用をおさえられますが、アスベストと地中埋設物は専門業者による撤去作業が必須となります。
特にアスベストの場合、解体工事前のアスベスト調査は法律で義務化されています。アスベスト建材は使用が全面禁止された2006年以降に建てられた建物であれば、除去費用が追加で発生する可能性があるので注意してください。
私の家の解体費用はいくら?
木造解体の手順
- 解体費用がいくらかわかったら、解体する手順をおさえよう!
木造解体の手順は、その他の構造(鉄骨造や鉄筋コンクリート造)の解体工事の手順と大きく違いがありません。
基本的には『解体工事前の準備』(所要期間1カ月~2カ月)と『木造家屋解体工事の手順』(所要期間10日~2週間)の2段階にわけることができ、工事前の準備は施主が、実際の施工は解体業者が主体で行われます。
実際にどのようにすすめるかは、次章以降でステップにわけて解説しています。
解体工事前の準備(9STEPS)
工事前の準備には通常1か月~2ヵ月かかり、おおきく9つのSTEPSにわけることができます。
▼解体工事前の準備(9STEPS)
- 情報収集
- 解体業者選び
- 現地調査
- 見積の比較
- 解体業者の選定
- 近隣への挨拶
- 残置物の撤去
- 補助金の申請
- ライフラインの停止
STEP1:情報収集
まずは情報収集と見積を依頼する解体業者を選びましょう。
木造の解体工事を始める前に、事前に解体費用の相場、工事にかかる期間、利用できる補助金制度をおさえておきましょう。
▼事前の収集がおススメな情報
| 情報 | ご参考記事 |
|---|---|
| 解体費用の相場 | |
| 工事にかかる期間 | |
| 利用できる補助金制度 |
上記の情報は解体工事に関する情報はインターネットからも調べられますし、相続などで家を解体した知人がいれば話をきいてみるのもひとつです。
費用の相場と工事の期間の目安としては、前述した通り、30坪の木造住宅の解体費用の相場は90万円~150万円で、工事にかかる期間は10日~2週間となります。
利用できる補助金制度については、家屋が空き家である場合、補助金を利用できる可能性が高いです。ご所属の自治体のホームページで制度がないか確認してみましょう。支給額は自治体ごとに異なりますが、おおむね解体費用の1/5~1/2、上限100万円とされているケースが多いです。
STEP2:解体業者選び
解体工事に関する知識がひととおりついた後は、解体業者に見積もりを依頼しましょう。
おススメは少なくとも2~3社に依頼することです。
解体業者にも特徴があり、木造戸建ての解体実績が豊富な業者もいれば、鉄骨造の大規模なマンションの解体を中心に扱っている業者もいます。また、見積もり金額は解体業者の経験値や重機の保有状況によって異なります。
できるだけ安価で安全に、対応よく施工を請け負ってくれる解体業者を見つけるには、比較できるように、複数社に見積もり依頼することが大切です。
STEP3:現地調査
見積を依頼すると、解体業者から連絡が入り、施主が希望する場合は現地調査が実施されます。
現地調査とは、解体業者が解体する建物に赴き、建物の状態や立地などの条件から解体費用がいくらになるか見積もることです。エリアや平米等の書面上の情報のみで見積もる場合もありますが、正確に金額を知りたい場合は現地調査の実施がおススメです。
現地調査では、劣化や損傷、耐震性などの建物の状態を確認します。また、建物内の設備や周辺の建物、道路、地下施設、地下水位などが調査され、解体作業に影響を与える要因を特定します。
現地調査自体は半日程度で終了しますが、調査依頼から調査完了までをふくめると、3日~7日かかるのが一般的です。
STEP4:見積の比較
相見積もりを依頼したら、工事費用の総額と内訳を確認しましょう。
解体工事では、建物本体の解体以外に足場や養成の設置、付帯物の撤去などの費用も別で発生します。建物の解体といった部分的な工事費用だけでなく、解体工事の総額をまとめて見積もってもらうようにしましょう。
稀に工事が始まってから追加費用を請求する悪徳業者も存在しますので、必ず工事の総額を最初に確認するようにしてください。
なお、解体業者によって現地調査を実施する際の評価の視点や、保有する機材の種類は異なります。解体作業員の技術力や、業者の拠点から現場への距離等にも違いは全て、解体費用に影響を与える要素です。よって、異なる解体業者から見積を取得する際は、内訳の詳細な比較と、「なぜこの金額なのか」の確認が重要となります。
また、見積書の形式も業者によって異なります。形式が違うので「なににいくら」かかっているのかを比較しづらいですが、工事の項目や施工範囲、数量、単価などをひとつずつ確認しましょう。
業者によっては見積書の内訳を「●●一式」とまとめて記載している場合があります。このような記載方法の場合、なににいくらかかっているのかを把握しにくいため、追加費用が発生した際に解体業者と交渉しづらくなります。よって、内訳の記載が荒い場合は業者に必ず確認し、細かくチェックしましょう。
STEP5:解体業者の選定
相見積もり後、どの業者に工事を依頼するかを決めましょう。
解体業者を選定する際は、単純に見積金額が最も安いという理由だけで業者を選ぶことはおススメできません。見積書や契約書の内容がわかりやすいか、坪単価は安すぎないか、連絡がスムーズにできるか、見積りに関する質問に対して曖昧な返答をしていないかを総合的に判断して決めましょう。
最終的にどの解体業者を選ぶか決めた後は、契約の締結を行います。契約書では、解体工事の施工内容や契約金額、工事期間及び支払い期限、工事完了の基準などを確認しましょう。
とくに着工から完工までのスケジュールを把握しておくと、後述する近隣への挨拶や補助金の申請、残置物の処分、ライフラインの停止などをいつまでの完了させておけばよいかのスケジュールもたてやすくなります。
STEP6:近隣への挨拶
解体工事では騒音や振動など、近隣に迷惑がかかるため、工事前に近隣への挨拶回りも忘れずに行っておきましょう。
事前に一言伝えておくだけでも、解体工事中のトラブルやクレームの発生を防ぐことができます。
挨拶回りの際は解体業者に同行を依頼するのがおススメです。騒音や振動、工事中の事故に対する防止策について質問された場合、専門家としての意見があるほうが納得を得られやすいためです。挨拶回りを代行してくれる業者もいますが、その際も施主として同行しておいたほうが、近隣とっての印象もよく、顔合わせができているのでトラブルが発生した場合も事態を収拾しやすくなります。
STEP7:残置物の撤去
建物内の家電や家具、衣類やゴミ等の残置物は、着工前までにできるだけ自分で廃品回収等で処分しておくことがおススメです。
残置物は自分で処分すれば「一般廃棄物」として自治体の規定金額で処分できますが、解体工事で処分する場合は「産業廃棄物」とされるため処分費用が割高になります。建物自体の解体が安く済んでも、廃材処分費用として残置物処分費用が追加されてしまうと、解体費用自体が高額となってしまいます。
自分で処分する場合、廃品回収等で粗大ごみとして処分しなくても、リサイクルショップなどの業者買取や、フリマアプリなどで売却するとお金をかけずに処分することもできます。
STEP8:補助金の申請
補助金を利用する場合は、必ず施工前に自治体へ申請を行います。
補助金申請をうけた自治体は、施工前に解体予定の建物を調査し、補助金の支給条件に該当するか確認します。よって、申請前に着工してしまうと、建物が補助金の支給条件に該当しているかわからないまま解体されてしまうため、自動的に給付対象から外れてしまうことがあります。
補助金の申請条件は自治体ごとで決められているため、各自治体のホームページをチェックしておきましょう。
STEP9:ライフラインの停止
解体工事前にライフライン(電気、水道、ガスなど)の停止手続きを行いましょう。
停止せずに解体工事を行うとライフラインが損傷し、火災、爆発、感電、ガス漏れなどが発生するリスクがあるためです。停止する際は、各供給会社に停止の日程と時刻(着工日と時刻)を伝え、それまで停止してもらうように手続きをしましょう。
私の家の解体費用はいくら?
木造家屋解体工事の手順(7STEPS)
工事前の準備が完了したら、いよいよ実際の施工が始まります。
施工(着工~完工)には通常10日~2週間かかります。施工の流れ(着工~完工)までは7つのSTEPSにわけることができます。
▼木造家屋解体工事の手順(7STEPS)
- 足場を確保して養生
- 木造家屋内の残置物を撤去
- 木造家屋内の内装材や設備を撤去
- 木造家屋の屋根を撤去
- 木造家屋の本体を重機で解体
- 地中埋設物やガラの撤去
- 木造家屋解体後の整地・清掃
以降で手順を解説していきます。
STEP1:足場を確保して養生
まず最初に解体業者によって行われるのは、足場の設置です。
足場の設置とは、建物や構造物を解体する際に、安全に作業できるように一時的に足場を組むことを指します。高所での作業時に、安全確保のために必要です。また、必要な工具や資材を持ち運びやすくなるため、スムーズに作業できるようになります。
次に養生を設置します。
養成シートで建物全体を覆うことで粉塵による近隣被害を防いだり、振動や騒音の影響をやわらげることができます。種類によって防音効果も異なるので、周辺に住宅が立ち並んでいる場合は効果が高いものを使用してもらうことがおススメです。
STEP2:木造家屋内の残置物を撤去
足場の設置が終わったら、家屋内の残置物を撤去します。
残地物とは、家屋内に残されている荷物や家具、家電などです。解体工事では建設リサイクル法により分別解体(資材を分別して処分すること)が法律で義務付けられており、解体工事前にすべて撤去されます。
STEP3:木造家屋内の内装材や設備を撤去
残置物を撤去した後は、家屋内の内装材や設備を撤去します。具体的には、壁パネル・天井材・床材・ドアや窓・照明器具・配管と給排水設備などがあげられます。
いきなり建物全体を重機で取り壊すのではなく、工具を用いつつ手作業でひとつずつ取り除いていきます。
STEP4:木造家屋の屋根を撤去
木造住宅の場合、屋根や塀に瓦が付帯している家屋もあるでしょう。
瓦はひとつずつ撤去していくので、屋根の面積が広いほど時間がかかります。一般的には1日~2日で全ての撤去を完了させることができます。
STEP5:木造家屋本体を重機で解体
瓦礫や内装材、設備を撤去したらいよいよ建物本体の解体です。
ただし、重機が入りにくい立地の場合は手作業で解体を行うことになり、工間が延び、費用が多くかかることを認識しておきましょう。
STEP6:地中埋設物やガラの撤去
建物本体を解体した後は、地中埋設物やガラの撤去を行います。
地中埋設物とは、地中に埋まっている埋設物や障害物のことで、電気やガスのためのケーブルやパイプライン、浄化槽や水道管などが該当します。放置しておくと地盤が緩みやすく、建て替えや新築後の漏水や損傷のリスクが大きくなります。水道管や下水道管の場合は特に顕著で、地下のインフラに影響を与える可能性があるため、必ず除去しておきましょう。
地中埋設物だけでなく、解体工事中に発生するガラも撤去の対象です。コンクリートガラは、手作業で拾って処分します。
STEP7:整地・清掃
地中埋設物やガラを撤去した後は整地・清掃を行います。
整地には様々な種類があり、解体後に土地をどう活用したいかによって適切な方法が異なります。住宅用地向けの、最もシンプルな整地方法は『荒仕上げ』と呼ばれ、地面を平坦にし、大きな不均等や地形を均にして行われます。
清掃は工事現場を元の状態に戻し、安全で清潔な環境にするために非常に重要です。特に解体後に土地を売ることをご検討中の方は、見栄えをよくすることで購入される可能性を上げることができます。
私の家の解体費用はいくら?
木造解体は自分でできる?
- 木造解体を自分でやれば費用を節約できる…?
小さな木造家屋の場合、費用を節約するために自分で解体できるか検討する方もいらっしゃるでしょう。
本章では木造解体を自分で行う場合の注意点と、かかる費用や準備するものについて解説します。
解体工事は自分でできる
結論からいうと、木造の解体工事は自分で行うことができます。
所有者が自分の家を解体してはいけないという法律はありません。(ただし、業者として解体する場合は解体工事業の登録が必要になります。)よって、必要な機材や重機を所有している方は、個人でも解体工事を行うことができます。
解体工事を自分でするための条件
ただし、解体工事を行うには次の条件を満たしている必要があります。
▼解体工事は自分でするための条件
- 重機操縦の資格をもっている
- 重機をレンタルできる
- 廃材置き場を確保できる
- 道路使用許可や建設リサイクル法の申請を自分でできる
- 自分で解体するリスクを許容できる
特に自分で解体する場合、それなりの手間やリスクを負うことになるので注意です。
例えば、アスベスト調査によってアスベストが含まれていると発覚した場合は、除去作業に危険が伴います。また、解体工事中に隣家を傷つけてしまったり、粉塵や騒音に対して近隣からクレームをうけた場合、自分でトラブル対処をしなければいけません。
解体業者に工事を依頼すれば、アスベスト除去だけでなく、近隣の挨拶周りから解体後の土地の整地にいたる、すべての工程を対処してくれます。費用はそのぶんかかりますが、自分で行う場合にリスクや手間を考慮すれば、安全かつ確実に工事を進められるといえるでしょう。
▼自分で家屋を解体する方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
私の家の解体費用はいくら?
木造を解体するならイエウール
木造解体の進め方について迷ったら、一括見積サイトのイエウールがおススメです。
全国の施工事例に詳しい解体専任のオペレーターが、ご自宅の状態にあった解体工事の進め方や、損しない見積もりの取り方、実績豊富な解体業者をご提案いたします。
私の家の解体費用はいくら?