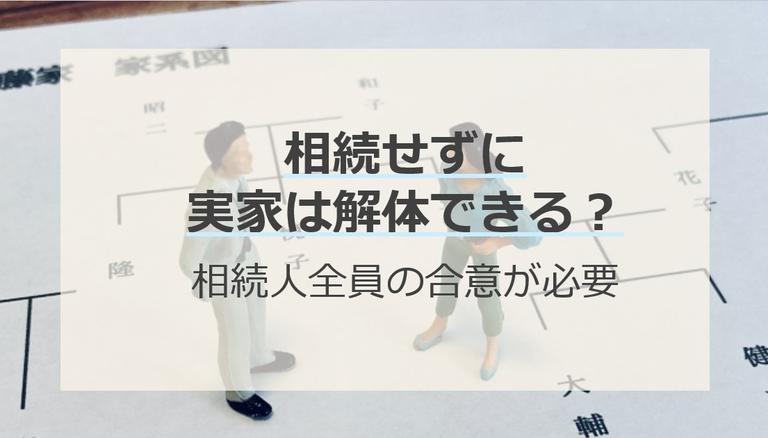私の家の解体費用はいくら?
弁護士。平成19年弁護士登録。平成22年より弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所入所、現在に至る。
中でも、不動産や賃貸契約に関する案件を多く扱い、不動産分野のコラム執筆やセミナー講師の経験を多数持つ。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
▼家の解体費用の基礎知識はこちらの記事で解説しています
相続手続せずに勝手に解体はできない
古くて市場価値がない家屋でも遺産分割の対象となるため、相続人全員の合意を得る相続手続きを経ずに、勝手に解体はできません。仮に相続せずに解体した場合、以下のリスクが発生してしまいます。
▼相続手続きせずに勝手に解体できない
- 損害賠償請求をうけるリスクがある
5年以下の懲役刑(2025年6月1日以降は5年以下の拘禁刑)となるリスクがある
以降で詳細を解説しています。
損害賠償請求をうけるリスクがある
相続人全員から合意を得ずに解体してしまうと、反対する相続人から損害賠償を請求された場合、応じなければならないリスクがあります。
名義変更前の実家は相続人全員の共有財産であるため、合意なしの解体は他の相続人の共有持ち分の侵害となります。
共有持ち分の侵害は、民法709条で不法行為に該当し、仮に他の相続人から損害賠償を請求された場合、請求に応じる責任が伴います。
民法709条【不法行為による損害賠償】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法709条|電子政府の窓口
5年以下の懲役刑(2025年6月1日以降は5年以下の拘禁刑)となるリスクがある
相続人の合意を得ずに解体した場合、刑事訴訟で5年以下の懲役刑(2025年6月1日以降は拘禁刑)になるリスクもあります。
2025年6月1日以降、刑法260条の「建造物損壊」における懲役刑と禁錮刑が統合され、「拘禁刑」として運用されるためです。
刑法260条【建造物等損壊及び同致死傷】
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
引用元:刑法260条|電子政府の窓口
相続人全員から合意を得ることは難しいかもしれません。しかし、上述したトラブルを考慮すると、合意を得ておくほうが負担は少なくすみます。
自治体命令で相続せず解体するなら、合意は必要ない
自治体が、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて行政代執行をする場合は、相続人全員の合意は必要ありません。
ここでいう行政代執行は、本来は相続人がすべき特定空き家等の解体を、相続人に代わって自治体が行うことを指しています。
なお、上記の場合は、自治体が相続人に代わって遺産である実家を解体することになり、相続人が解体するわけではありません。
相続せずに解体する際のその他の注意点
相続せずに実家を解体する場合、いくつかの注意点があります。
▼相続せずに解体する際のその他の注意点
- 土地や建物の名義人を正しく把握する
- 解体を検討する建物の住宅ローン残高を把握する
以降で詳細を解説しています。
土地や建物の名義人を正しく把握する
土地や建物の名義人が誰かはしっかり確認しましょう。実家の名義人が両親だと思っていたら、実は祖父母名義というケースはよくあります。
実家の名義人が両親の場合と祖父母の場合では、相続人の人数が異なります。相続人が複数いる場合、合意形成が煩雑化します。
誰が相続人に該当するのか把握するためにも、相続人の名義は必ず確認しておきましょう。
解体する建物の住宅ローン残高を把握する
住宅ローンが残っている場合、金融機関などが建物の抵当権を持っている可能性があります。
抵当権つきの家は、建物や土地が住宅ローン返済の担保とされています。よって、抵当権つきのまま建物を解体してしまうと、返済に関して金融機関とトラブルが発生するリスクが高いです。
よって、まずは住宅ローンを完済し、抵当権の抹消手続きを終えてから解体するようにしましょう。
私の家の解体費用はいくら?
相続せずに家を解体する流れ
本章では、相続登記せずに家を解体する流れを解説しています。
| 担う人 | 流れ |
| 施主 | 相続人全員から合意を得る |
| 施主 | 相続人が複数の場合は全員の合意を得る |
| 施主 | 見積もり取得・業者選定 |
| 施主 | 近隣の挨拶周り、ライフラインの停止 |
| 業者 | 解体工事を行う |
| 相続人 | 建物滅失登記をする |
【施主】相続人全員から合意を得る
まずは相続人から解体について合意を得ましょう。
例えば、親名義の家を解体する場合、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。そして、親族に、①子供がいれば子供が相続人に、②子供がおらず、両親がいれば、両親が相続人に、③子供も両親もおらず、兄弟がいれば兄弟が相続人となります。
相続人が複数人いる場合は、全員の合意を得て工事を進めるようにしましょう。また、誰が解体費用を支払うのか、建物滅失登記は誰が行うかも決めておくことがおススメです。
特に、解体費用を誰が支払うかは相続人間でもめるポイントなので、よく話し合って決めるようにしましょう。
▼解体費用を誰が支払うかについてはこちら
▼兄弟のうち解体費用をどちらが支払うか揉めた場合はこちら
【施主】見積もり取得・業者選定
家の解体について相続人から同意を得たら、2~3社の解体業者から見積もりを取得し、解体業者を選定しましょう。
見積もりを取得する場合は、解体したい家の近くにある、実績がある業者を選ぶことが大切です。
また、解体工事業に登録している、あるいは建設業許可を取得しているなど、事業会社として信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
【施主】近隣の挨拶周り、ライフラインの停止
解体業者を選んだら、近隣の挨拶周りと、ガスや電気などのライフラインの停止を行います。
解体工事を行うと、騒音や粉塵などで近隣の生活環境を悪化させます。
よって、挨拶なしで工事をすると周辺住民からクレームが発生するリスクがあります。
また、ガスや電気等のライフラインを停止せずに工事を行うと、工事中に水道管やガス管が爆発して事故につながってしまいます。
安全に工事できるようにするために、挨拶周りとライフラインの停止は必ず行うようにしましょう。
【業者】解体工事を行う
解体工事の準備が進んだら、解体業者が解体工事を行います。
解体工事は、足場や養生の設置、建物の解体、廃材の処分、整地の順に進み、一般的な住宅なら、工事期間は3日~10日が平均的です。
【相続人】建物滅失登記をする
建物滅失登記とは、建物が解体されてなくなったことを記録するための手続きで、建物を解体した後1カ月以内の実施が必須となります。
建物滅失登記を行うことは法律で義務付けられているため、期限内に実施しましょう。(不動産登記法第57条)
なお、建物滅失登記は建物の相続人でなければ行うことができないので注意してください。
私の家の解体費用はいくら?