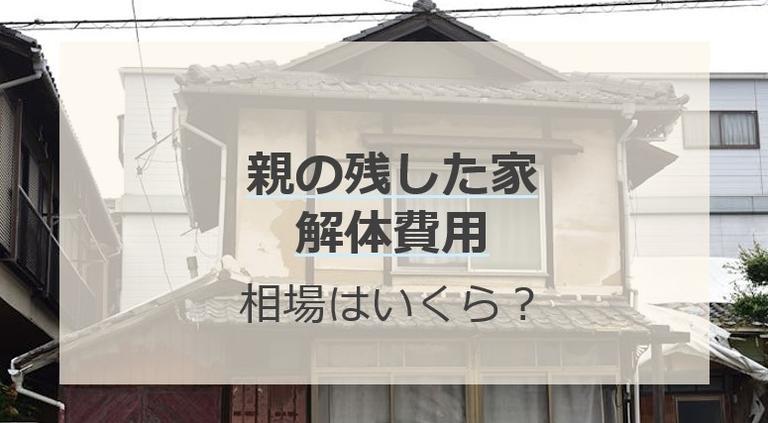「親が残した家を解体するといくら?」
親が残した家を相続して解体する場合、解体費用はいくらかかるのか、誰が支払うのか、気になりますよね。
本章では、親が残した家の解体を検討している方にむけて、かかる費用相場、誰が支払うのか、相続から解体して売却するまでの流れ、実家を解体するメリットとデメリット、を解説しています。
私の家の解体費用はいくら?
▼解体費用の基礎知識について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
親の残した家の解体費用はいくらになる?
まずは解体費用がいくらになるか確認していきましょう。
解体費用の相場は100万円~200万円
解体費用の相場は100万円~150万円といわれています。
ただし、上記はあくまでも相場で、実際の費用は立地や付帯物の有無等、様々な条件によって左右されます。
私の家の解体費用はいくら?
解体費用の決まり方
家の解体費用は様々な要素によって変動します。
▼解体費用の決まり方
- 家の構造
- エリア(地方か都心部か)
- 重機が使用しやすい立地か
- 付帯物の多さ
- 残された家財や荷物の多さ
- アスベスト・地中埋設物の量
家の構造
親が残した家が木造であれば3万円~4万円/坪、鉄骨造なら5~7万円/坪、鉄筋コンクリート造なら6~8万円/坪といわれています。
▼構造別の相場
| 構造 | 坪単価 | 30坪 | 50坪 |
| 木造 | 3万円~4万円 | 90万円~120万円 | 150万円~200万円 |
| 鉄骨造 | 5万円~7万円 | 150万円~210万円 | 250万円~350万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 6万円~8万円 | 180万円~240万円 | 300万円~400万円 |
私の家の解体費用はいくら?
エリア(地方か都心部か)
都心部から離れれば離れるほど、解体費用の坪単価は安くなる傾向にあります。
【田舎】
| エリア | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 2.6万円 | 3.7万円 | 4.9万円 |
| 島根 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.7万円 |
| 徳島 | 2.6万円 | 3万円 | 5.2万円 |
| 三重 | 2.5万円 | 3.5万円 | 4万円 |
【都心部】
| エリア | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 4万円 | 5.3万円 | 7.7万円 |
| 大阪 | 4.1万円 | 5.1万円 | 8万円 |
| 名古屋 | 3.8万円 | 5.6万円 | 7.5万円 |
| 福岡 | 4.9万円 | 5万円 | 8万円 |
私の家の解体費用はいくら?
重機が使用しやすい立地か
【重機が使用しやすい立地の特徴】
- 前面道路の幅が広い(4m以上)
- 隣接地との距離が遠い(1m以上)
- 重機を駐車するスペースがある etc…
上記の特徴をもつ立地の場合、重機が入りやすいまたは使用しやすい立地のため、手作業が増え、解体費用が高くなります。
特に住宅が密集した区域に建っている実家の場合に該当するケースが多いです。
解体工事で手作業が増えると、工事の期間が延びてしまいます。解体費用の約6割は人件費(=作業員への日当)で構成されてるため、解体工事期間が延びるほどかかる費用も高くなってしまいます。
付帯物の多さ
建物を解体する際は付帯物も同時に撤去する必要があります。
付帯物の撤去は建物の解体前に手作業で行われるため、付帯物の量が多いほど作業に時間がかかり、解体費用が高くなります。
▼付帯物撤去費用の種類と相場
| 撤去工事費用 | 付帯工事費用 |
| カーポート撤去費用 | 6万円~/1台用 |
| ブロック塀撤去費用 | 5,000円~1万円/1㎡ |
| 植物の撤去費用 | 5,000円~3万円 |
| 門扉の撤去費用 | 2万円程度 |
| 倉庫・物置の撤去費用 | 2万円~3万円 |
| 浄化槽の撤去費用 | 5万円〜10万円 |
| 井戸の埋め戻し | 3万円〜5万円 |
また、前面道路の道幅が狭い、隣接地との距離が近い、駐車スペースが狭いなど、重機が使用しづらい立地の場合も手作業が増えることで解体費用が高くなりやすいです。
残された家財や荷物の多さ
家の中に荷物や家電などの家財が残されているほど、解体費用は高くなります。
荷物や家財は『残置物』と呼ばれ、解体工事で廃棄される場合、産業廃棄物として専用の廃棄物処理場に運搬され、処理されます。
産業廃棄物の処分費用は、廃棄物処理場によって左右されますが、自分で処分するよりも割高になります。
自分で処分すると、一般廃棄物として処分されます。一般廃棄物として地域の廃品回収に出す場合、自治体から処分費用の補助を一部うけることができます。
また、自分で処分する場合は、リサイクルセンターや買取業者に売る等、費用をかけずすむ方法もあります。
着工の段階で荷物や家財が残されているほど、処分費用は高くなってしまいます。よって、工事前にできる限り自分で処分して、費用をおさえることがおススメです。
アスベスト・地中埋設物の量
▼アスベスト・地中埋設物の量
| 撤去工事の内容 | 撤去費用 |
| アスベストの撤去費用 | 2万円〜8.5万円(含まれている面積が300㎡以下の場合) |
| 地中埋設物撤去費用 | 5,000円~/㎡ |
解体工事前後にアスベストや地中埋設物が発見された場合、撤去費用が追加で発生します。
アスベストとは建材の一種で、人体への有害性から2006年に使用が禁止され、解体工事前は撤去することが法律で義務付けられています。また、地中埋設物とは地面に埋まっているコンクリートや木くず、浄化槽等のことです。解体後に建物が安定して建設しづらくなるため、除去が必須となります。
家個別の条件を踏まえたうえで、ご自宅の解体費用がいくらになるかを見積もることができます。
私の家の解体費用はいくら?
親が残した家の解体費用は誰が負担する?
実家の解体費用は原則、相続人が支払います。
ただし、相続人が複数いる場合、相続人のうち誰が支払うのかは次のようにわけることができます。
▼親が残した家の解体費用は誰が負担する?
| 状況 | 誰が支払うか |
|---|---|
| 1人が家を相続した | 相続した実家の名義人 |
| 複数人で家を相続した(=共有名義) | 相続した共有名義人全員 |
| 誰も相続していない | 相続人同士で話し合って決める |
【1人が相続した】相続した家の名義人が支払う
実家の相続を終えた相続登記済みの実家の場合は、実家の名義人が解体費用を支払います。
実家の所有権は登記謄本に掲載されている名義人にあるため、名義人に解体費用の支払い義務が発生します。
【複数人で相続した】共有名義員全員が支払う
複数人で共有名義として相続した場合は、解体費用を共有名義人の人数で分割して支払います。
ただし、分割を決める際は名義人全員の合意が必要です。分担を決める際は、トラブルに発生しやすいため、必要に応じて弁護士などの専門家からアドバイスをうけましょう。
【誰も相続していない】相続人同士で話し合って決める
誰も相続していない実家の場合は、遺産分割協議で相続する人を決めるか、全員が相続せずに費用をどう分担するかを話し合いましょう。
解体後に土地を売ることを検討している場合は、
- いったん全員で負担して土地の売却代金を分割する
- 特定の相続人が解体費用を建て替え、売却代金を分割する際に立替分を回収する
などの方法があります。
家の解体費用は個人にとって大きな負担なので、誰もが支払いを渋ると思います。
しかし、解体後に売却する場合は、売却代金を解体費用にあてることができるので、支払いの負担も決めやすくなります。
私の家の解体費用はいくら?
親の残した家を解体する流れ
親が残した家は次の7つのステップで解体していきます。
▼親の残した家を解体する流れ
- 解体費用の見積もりをとる
- 遺産分割協議
- 近隣住民への挨拶
- 解体工事
- 建物滅失登記
- 空地の相続登記申請
- 空地の売却
ステップ①解体費用の見積もりをとる
解体工事の見積もりを取る際には、必ず2~3の解体業者から相見積もりを取得しましょう。
複数の会社の見積もりを取ることで家の解体費用相場を把握できます。
適正な費用の解体業者を選ぶ際に役立つほか、値下げ交渉の材料にもなるため、できれば多くの会社に問い合わせることをおススメします。
ステップ②遺産分割協議
財産の分割方法を決める相続人同士の会議は、遺産分割協議と呼ばれます。
決定事項を書面に書き起こす義務はありませんが、各相続人が書面として持っておけば、聞いていない等のトラブルを事前に防ぐことができます。
遺言書がない場合や、法定相続分と異なる割合の分割を行う場合は、遺産分割協議書の作成が重要となりますので気をつけましょう。
ステップ③近隣住民へ挨拶
解体工事は騒音が伴うので、工事前に近隣住民への挨拶を済ませておきましょう。
また、電気やガスなどのライフラインの停止も忘れずに行ってください。
ステップ③解体工事
協議が終われば、次は家の解体です。期間は約1〜2ヶ月ほどかかります。
重機を搬入させる前に、庭木や塀などの外構を解体します。
その後、重機の搬入と足場の設置が行われ、屋根や内装、建物本体と基礎を随時解体していきます。
建物本体を解体した後は、土地を綺麗にして周辺を清掃し、依頼主の最終確認が済み次第、解体工事は完了です。
ステップ⑤建物滅失登記
解体工事が済んだ後は、建物がなくなったことを登録する「滅失登記」を行う必要があります。
滅失登記は、建物がなくなった日から1ヶ月以内に申請をしなければならず、期限内に申請されない場合には10万円以下の過料が課されますので注意しましょう。また滅失登記がされない場合には、建物の取り壊しが済んでいる場合でも登記上は建物があるとみなされてしまうので、固定資産税が課されてしまうリスクもあります。
ステップ⑥空地の相続登記申請
相続登記は、現在の所有者を明確にするための手続きです。
土地を売却する場合は特に、名義が故人のままでは売却を進められないため、相続登記を行う必要があります。
また、相続人の負債で土地が押さえられるリスクもあります。登記簿謄本の情報は権利関係で第三者に対抗する際に重要なので、常に最新にしておきましょう。
ステップ⑦空地の売却
登記関係が終われば、あとは土地の売却です。
売却の際は仲介業者を挟む場合がほとんどなので、仲介手数料が発生します。
また、土地売却で得た利益(譲渡所得)には所得税と住民税がかかるため、注意が必要です。
譲渡所得にかかる税金は、土地の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得といい、税率は約40%です。5年超えの場合は長期譲渡所得といい、約20%の税率が適用されるため、短期と比較して半分の税金で済みます。所有期間は故人が土地を取得したタイミングから起算されますので、確認の際は気をつけてください。
私の家の解体費用はいくら?
親が残した家を解体するメリット・デメリット
| 親が残した家を解体するメリット |
|
| 親が残した家を解体するデメリット |
|
詳細は以降で解説しています。
【メリット①】更地のほうが売れやすい
解体して更地にしたほうが、古い建物が建っている土地よりも買い手がつきやすくなります。
更地の場合、土地の用途が多様であるため、より多くの購入者にとって最適な土地となりえるためです。
対して、建物が建っている土地の場合は、建物つきで利用することで条件が制限されてしまいます。購入後に解体する場合は、買い手自身が費用を負担しなければいけません。
特に田舎にある実家の場合は、もともと買い手が少ないため、建物つきだとなかなか売れない可能性もあります。更地にすることで幅広い購入者に訴求できるため、早く・高く売れるといれるでしょう。
【メリット②】現金で遺産分割できる
更地にして土地を早く・高く売ることができれば、現金で遺産分割できます。
土地と家で相続する場合、複数の相続人で分割することは難しいです。共有名義で相続したとしても、売却や活用には共有人全員の同意が必要になります。
また、代替わりがあった場合は、親から子、子から孫へ、共有名義人が雪だるま式に増えてしまうリスクもあります。
更地にすることで売却しやすくし、早急に現金化することで、現金で公平に遺産を分割でき、相続時のトラブルを防ぐことができます。
【メリット③】相続から3年以内に売れば譲渡所得税を控除できる
相続から3年以内に土地を売却した場合、譲渡所得税を控除できます。譲渡所得税とは、土地の売却益に課せられる税金のことです。
譲渡所得税の税率は売却益の約20%となっていますが、控除を利用することで課税譲渡所得を減らし、節税することができます。
相続から3年以内に売却した場合に使える控除は「相続空き家の特例」と呼ばれ、課税譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
参考|国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
【デメリット①】再建築不可の土地は売れにくくなる
更に、実家を解体し更地になった状態で再度家を建てようとしても、同じようには再建できない可能性があるため注意が必要です。
これは実家が建てられたタイミングと現行の建築基準法が異なる場合に起こりうります。当時の法律上は建築可能でも、現行の法律では建築できないためです。
更地にした後に土地のみの売却を検討している場合でも、新しく建築できない土地であれば売却自体が難しくなってきます。
解体後の用途によって本当にそれができるのかを確認しておくと安心でしょう。
【デメリット②】建物つきで売れる場合もある
立地がよい(都心部に近い、交通の便がよい、生活施設が周辺にある)土地の場合、建物つきでも売ることができます。
建物つきで売ることができれば、解体費用を誰が負担するかで揉めたり、実際に負担して資金を減らすこともありません。
実際に建物つきでも売れるかどうかは、実家周辺の不動産会社に相談したり、いちど市場に売り出してみることで傾向がわかります。
【デメリット③】解体の翌年から固定資産税が上昇する
解体工事の翌年から固定資産税は上昇します。
建物つきの土地は、政府の特例(住宅用地の特例)で税率が最大1/6まで軽減されています。
実家を解体し土地が更地になる場合、特例の適用対象外となり、税額が最大6倍まで戻ります。
解体後に土地を保有し続ける場合は、上昇した固定資産税を支払い続けることになる点に注意しましょう。
私の家の解体費用はいくら?