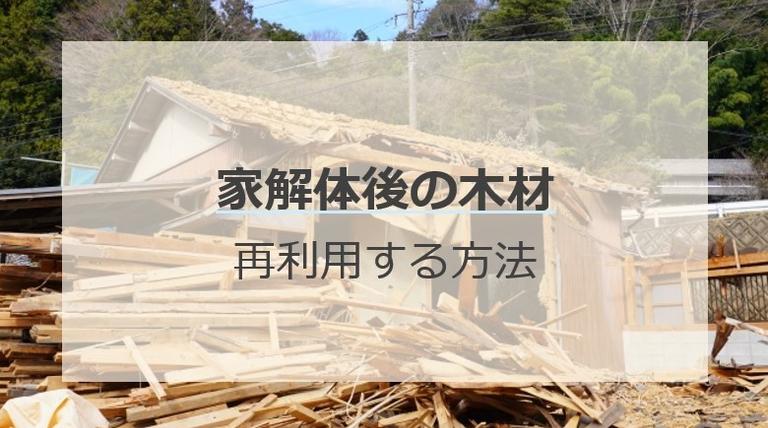「家の解体後の木材再利用って義務?」
解体後の木材の再利用は建設リサイクル法により義務付けられています。
違反すると罰則が科される可能性もあります。なお、再利用できる木材には、梁や大黒柱、欄間などが含まれます。
ただし、再利用には適切な手順と注意点があり、専門の解体業者への依頼が推奨されます。
私の家の解体費用はいくら?
家解体後に木材を再利用するのは義務
建設リサイクル法は、分別解体と再資源化が義務付けられた法律です。分別解体とは、コンクリート、木材、アスファルトなどの資材をそれぞれ分別して取り出し、リサイクル可能なカタチにすることです。
床面積が80㎡以上の解体工事が対象
また、再利用の対象となるのは、延べ床面積が80㎡以上の家屋のみです。
▼建築リサイクル法 第十六条
- 建設リサイクル法による対象建設工事となる建築物の解体工事は、特定建設資材を用いた建築物に関する解体工事であって、建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号)の全部又は一部について、床面積の合計で80㎡以上を解体する工事である。
私の家の解体費用はいくら?
家解体後に再利用できる木材の種類
再利用できる木材は次の5種類にわけることができます。
▼建材の主要構造材
| 種類 | 概要 | 利用方法 |
| 梁(はり) | 建物の屋根や床を支える水平の主要構造材 | 新築の梁、玄関の踏み台や柱、家具等のインテリア |
| 大黒柱 | 家の中心を支える構造的に重要な太い柱 | 新築の板材、家具等のインテリア |
| 鴨居(かもい) | 引き戸の上部に設置される横木 | 新築の引き戸、窓の支持材 |
| 欄間(らんま) | 和室の仕切り上部にある採光・通気用の板や格子 | 部屋間の仕切り、家具等のインテリア |
| 蔵戸(くらど) | 蔵の入口に使われた厚く頑丈な木製の扉 | 新築の玄関ドア |
梁(はり)


参照:古材日和スタッフブログ_古材梁の販売は古材日和!活用事例と選び方をご紹介!
特に古い家の梁は、形を活かしたまま新築の梁として再利用されることがあります。例えば、規格に合わせて加工し、あえて梁を見せる「古民家風住宅」を実現するケースです。また、再利用が難しい場合でも、玄関の踏み台や柱、インテリアとしてのオブジェに活用可能です。
大黒柱

参照:青森ひば・住宅資材・住宅ローンのことなら新ナガモク|大黒柱の画像

参照:RoomClip
主に新築で板材として再利用される価値があります。難しい場合には、ローテーブルやシューズ棚など、インテリアとして再利用できます。
鴨居(かもい)

参照:古材日和スタッフブログ_【古材の使用事例】古材の鴨居でテーブルを作ってみました!!

特に古い鴨居は再加工して、新築住宅の引き戸や窓の支持材として再利用することが可能です。また、画像のようにテーブル等の家具やインテリアにも使用できます。
欄間(らんま)

参照:RoomClip

参照:RoomClip
再利用例として、部屋間の仕切りや縁側との境界装飾、新築のアクセントとなる和モダンなテーブルや照明、玄関インテリアなどがあります。
蔵戸(くらど)

参照:RoomClip

蔵戸はけやき等の高級木材で作られ、頑丈で厚みがあるため、新築の玄関ドアとして再利用するのに最適です。引き戸を開き戸に変えたり、格子にガラスを組み込むなどの加工を施すことで、現代的な使用感を実現できます。
再利用時は、傷をつけないように解体することが求められます。また、適切に乾燥処理や殺菌処理を行うことが重要です。これらの条件や木材の特徴を考慮して、資源を無駄にせず、環境負荷の低減に努めることが法的にも社会的にも求められています。
私の家の解体費用はいくら?
家の解体後の木材の再利用方法2つ
家の解体後の木材の再利用方法には、「自分で再利用する方法」と「業者が再利用する方法」の2つがあります。
▼家の解体後の木材の再利用方法
| 方法2つ | メリット | デメリット |
| 自分で再利用する方法 |
|
|
| 解体業者に依頼する方法 |
|
|
自分で再利用する方法
自分で再利用する場合、まず再利用可能な木材を自分で選別し、加工することが必要です。
自分で再利用する最大の【メリット】は、コストを抑えられる点です。業者に依頼する費用が不要で、材料費だけで済むため経済的です。また、DIYならではの個性を生かして家具やインテリアを制作でき、オリジナル性の高い作品を生み出せます。
ただし、【デメリット】として多くの時間と労力が必要です。木材を加工するためには専門的な工具や技術が必要で、不慣れな場合はケガのリスクや仕上がりの質に不安が残ります。さらに、木材の保管や作業スペースが必要となり、特に都市部ではスペース確保が課題です。工具や防腐剤などの材料費が初期投資として発生する点も負担となる可能性があります。
解体業者に依頼する方法
解体業者に再利用を任せる最大の【メリット】は、プロの技術と専門知識によって安全かつ効率的に木材を再利用できる点です。
特に、木材を傷つけることなく適切に取り出し、建材やリサイクル製品に再加工するため、仕上がりの品質が保証されます。また、解体から再利用まで一括で依頼できるため、時間や手間を大幅に省くことできます。さらに、環境に配慮したリサイクルのプロセスを業者が担うことで、廃材の有効活用と環境保護に貢献できます。
【デメリット】としては、費用がかさむことが挙げられます。プロに依頼する手数料や解体費用、木材の再加工費用が発生し、自分で再利用する場合と比べて経済的負担が大きくなります。
また、業者によっては木材の再利用が限定的で、希望する用途に対応できない場合もあります。さらに、木材の選別や再利用方法が業者任せになるため、個人の思いやこだわりが反映されにくい点もデメリットです。
私の家の解体費用はいくら?
家の解体工事から木材再利用までの流れ
家の解体から木材再利用までには、いくつかの重要なステップがあります。以下では、解体工事の開始から新築での取り付けまでの流れを詳しく解説します。
▼家の解体工事から木材再利用までの流れ
- 解体業者選び
- 解体工事の開始
- 再利用する木材の選定
- 木材の加工
- 新築へ木材の取り付け
解体業者選び
まずは古材を再利用する際の解体業者を選びましょう。
【実績】については、過去の施工事例や口コミを確認し、適切な解体技術を持っているか確認することが大切です。
【リサイクルネットワーク】や【専門知識を持つスタッフ】ががいる場合、スムーズにことが進むことが多いです。
【費用】は事前に明確な見積もりを取り、追加料金の有無を確認してください。【解体業者としての資格】(許可や産業廃棄物収集運搬許可)を持つ、信頼できる業者を選ぶことも重要です。
解体工事の開始
木材再利用の第一歩は、解体工事です。
通常の解体工事では廃材が一括して処理されることが多いですが、再利用を希望する場合は「分別解体」を行う必要があります。
この方法では、再利用する木材を傷つけないよう慎重に取り外します。
再利用する木材の選定
解体工事が進む中で、再利用に適した木材を選定します。
この段階では、業者と一緒に木材の状態を確認し、再利用可能な部分を見極めることが大切です。また、どの部分をどのように再利用するのか、具体的なアイデアを相談しながら進めるとよいでしょう。
木材の加工
選定した木材は、そのままでは再利用が難しい場合が多いため、加工が必要です。
加工作業は、再利用後の木材が新しい家で十分な耐久性と美観を保つために不可欠です。専門の職人や業者が対応する場合が多いですが、DIYで加工する選択肢もあります。
新築へ木材の取り付け
加工が完了した木材は、新築やリフォームの建築現場で取り付けられます。
特に梁を柱として使う場合、建物の構造を支える重要な役割を果たすと同時に、ヴィンテージ感のあるデザイン性を加えることができます。
また、家具や内装材として取り付ける場合は、日常的にその木材を目にすることで家族の思い出を感じられるでしょう。
私の家の解体費用はいくら?
家の解体時に木材を再利用する際の注意点
本章では、家の解体時に木材を再利用する際の注意点を解説します。
▼家の解体時に木材を再利用する際の注意点
- 新調するより費用がかかるケースもある
- 解体工事前に再利用したい旨を業者に伝えておく
- 再利用できない木材もある
- 再利用が得意な業者を選ぶ
新調するより費用がかかるケースもある
木材を再利用する場合、新調より費用がかかることがあります。
例えば、古材の汚れや傷を除去したり、強度不足を補強する作業には追加の費用が必要です。
新品の木材は規格化されており効率よく利用できますが、古材はその都度調整が必要なため、結果的に高くつく場合があります。
解体工事前に再利用したい旨を業者に伝えておく
再利用したい旨は、解体工事前に必ず業者に伝えましょう。
分別解体では、木材、鉄くず、鉄筋コンクリート等のすべて資材を、解体工事後に再利用するために分別します。
解体業者に事前に伝えておかない場合、工事前に他の建材と一緒に分別されてしまうので、再利用したい木材が混在してしまうケースも珍しくありません。
また、取り除かれた木材は別途保存や運搬されますが、ここでも追加費用が発生するため、早めの相談が必要です。
再利用できない木材もある
解体後の木材すべてが再利用できるわけではありません。
腐食やシロアリ被害を受けた木材は、強度不足や衛生面で問題があるため、再利用には不向きです。また、湿気を多く含んでいる木材はカビのリスクが高く、再利用前に乾燥処理が必要ですが、それでも利用できない場合があります。
その他、防腐剤や防虫剤が使われた木材は、新しい家での使用が法律で制限される場合や、安全性に懸念がある場合があります。塗装や接着剤が多用された木材は、加工が困難で再利用が制限されることがあります。
再利用が得意な業者を選ぶ
再利用が得意な業者を選ぶとは、木材の再利用を前提とした解体や加工の経験が豊富で、適切な提案や作業ができる業者を選ぶことを指します。
再利用が得意な業者は、解体時に再利用可能な木材を丁寧に取り外す「分別解体」の技術を持ち、木材の状態を見極めるノウハウも備えています。
さらに、再利用が得意な業者は、過去の事例を基に具体的な活用方法を提案してくれることが多いです。また、保存や運搬の方法についても適切な指示をくれるため、木材が劣化せずスムーズに再利用できるのも特徴です。
私の家の解体費用はいくら?
解体後に木材を再利用するならイエウール
家の解体から木材の再利用までを一括で依頼するなら、「解体業者」に任せるのが最適です。
リフォーム会社や工務店、建設会社でも対応可能な場合がありますが、これらの業者では解体の際に木材が傷ついたり、適切に取り出せなかったりすることがあります。解体用の専門設備が整っていないケースも少なくありません。
その点、解体のプロである解体業者なら、再利用を考えた木材を傷つけることなく丁寧に取り出すことが可能です。「大切な思い出の木材を壊してしまった」という後悔を防ぐためにも、専門知識と技術を持つ解体業者に依頼することをおすすめします。
私の家の解体費用はいくら?